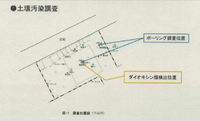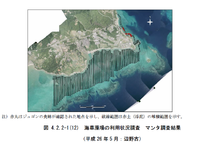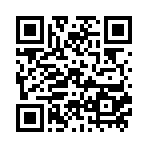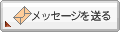キャンプ瑞慶覧・西普天間:公開されない現場写真(2)環境補足協定の面から
2015年02月23日/ 日米地位協定/ 環境協定/ キャンプ瑞慶覧/ 基地返還跡地/ 汚染/ 西普天間/ 沖縄県環境政策/ 沖縄防衛局
キャンプ瑞慶覧・西普天間:公開されない現場写真(1)に続いての記事です。
沖縄県への要請
この公開されない現場写真については、米軍が公開しない、ということで米軍を非難するのみでなく、沖縄県を動かしていく必要があるということを、沖縄県の環境政策を見ていくNGOとして考えていきたいと思います。
それは、沖縄県が米軍基地への立ち入り調査を要請しているわりには、実際、コトがおこった時に具体的で積極的な姿勢がみえないからです。
宜野湾市への要請書の写しを沖縄県に送る時に、以下のような要請を書きました。
沖縄県と環境条項
環境条項の面からの取り組みとは何か?
沖縄県は、基地への立ち入りや汚染調査に関する、日米地位協定の見直しを要求してきた経緯があります。
沖縄県サイト 「日米地位協定の見直しに関する主な経緯」 (2014年8月14日までの更新)
環境条項が地位協定に含まれていないことが問題視され、軍転協、渉外知事会などでも要請事項となってきました。
特にこの1,2年、政治的な文脈--前県知事の辺野古の埋め立て承認の問題--と絡めて、西普天間の返還、そしてそれに伴う立ち入り調査の件は「基地負担軽減」の一つとして扱われてきました。
2013年10月3日の「日米安全保障協議委員会共同発表「より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて」では、「2013年11月末までに,返還を予定している米軍の施設及び区域への立入りに関する枠組みについての実質的な了解を達成することを決定した。」と発表され、同年10月24日に行われた第2回 駐留軍用地跡地利用推進協議会では仲井真知事(当時)が掘削を伴う返還前の立ち入り調査を要請しています。
この件に関しては、立ち入りの枠組みを決めるための検討が必要であると沖縄BDから要請書を出しています。[返還跡地問題]2+2:立入り調査の枠組みについての要請(2013.11.22)
それが非常に露骨な形で現れたものが、当時の仲井真県知事による辺野古新基地建設のための埋め立て承認の直前、2013年12月に政府に提出した沖縄県の要請書です。2.の基地負担軽減の部分が立ち入り調査などの件が要請事項として記されている部分です。
そもそも、このような調査の権利は、当然あるべき権利としてみなすべきで、その権利を要求することは、「負担軽減」の範疇にいれてはいけないことだと考えます。また、政治的取引の材料として議論されるべき問題でもありません。
その沖縄県要請書はこちら。
この後、2014年6月24日返還前の掘削を伴う埋蔵文化財調査についての日米合意があり、8月15日から、宜野湾市による立入り及び調査が可能となります。(この経緯についてはキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区の汚染調査などに関するこれまでの経緯の記事参照)
そして、この問題は、2014年11月の県知事選前に再び浮上します。10月20日、日米共同合同発表で米軍基地内の環境調査や日本側の立ち入りや環境基準などを定める補足協定を実質合意したと発表します。これは当時の現職、仲井真知事への後押しであると解釈されています。
日本の環境基準維持 基地内調査で合意発表 (沖縄タイムス 2014.10.21)
この合意書全体についての問題は、ここでは言及しませんが、立ち入りに関する原文の該当部分を切り出しておきます。

語彙も非常に曖昧ですし、具体性に欠け、米軍の裁量によって左右されるという問題が解決される保証はないい、ということは明白です。
これに対して、QABニュースでコメントしました。県内紙でも桜井国俊さんや砂川かおりさんがコメントなさっていましたがクリッピングがおぼつかず。

QAB環境協定で実質合意(2014.10.21)
朝日新聞でもコメントしました。
朝日新聞「米軍基地に新環境基準 地位協定補足、自治体調査ルール化へ」(2014年10月21日)
県政のやるべきことは?
結局、知事選はこの後押しも効力はなかったのか翁長雄志氏が知事選に勝利しました。骨抜きの環境協定は提示されたままの状態で、まだ仕切り直されていません。
翁長県政でこの部分を仕切りなおすことは、嘉手納より南の返還計画とともに「基地負担」の部分を問いなおすこととともにやっていかなければならないことでしょう。
沖縄市サッカー場問題が政治問題として利用されてしまった面があることは忸怩たる思いがありますし、一つ一つ声をあげきれていないことは反省点です。しかし、翁長県政に変わったことをきっかけに具体的に県政に問題提起をしていくことは重要だと思っています。
この間、沖縄県は何をしていたかといえば、2014年度から沖縄県基地環境特別対策室を一括交付金事業として立ち上げています。その中で、米軍施設環境対策事業検討委員会を設置し、”基地返還予定地及び返還跡地における環境問題や在沖米軍の活動に起因する環境問題に対応するため、米軍施設における環境情報の構築と環境対策方針を策定し、国と連携した新たな環境保全のしくみ及び米軍施設とその周辺における環境情報をまとめた環境カルテを作成する予定”しているそうです。
沖縄県HP:米軍施設環境対策事業検討委員会
QAB 米軍施設環境対策事業検討委員会 (2015.2.7)
この会議の中でも、委員から「環境に関する基本的な事項については、米軍との間で情報交換ができるような仕組みを作って欲しい。」という(いまさらの)意見がでています。県の回答は「ご指摘の趣旨を踏まえ、米軍環境部門と情報交換をはじめられるよう、調整していきたい。 」という行政お得意の「調整」回答です。
しかし、現実は元跡地で、返還予定跡地の文化財調査で汚染が発覚しています。実際は現実に起こっている問題で交渉力を鍛えていくこと、米軍との交渉を防衛局任せにせず、日本政府との庇護的・パターナリスティックな関係を断ち切っていくことが県の環境政策には必要であるのではないか、と思います。
写真を出す交渉くらい、カルテとかしくみとか出来上がる前にできるでしょう。そして、これを材料に実質的な内容を伴う環境補足条項の締結を日米に要請し、その要請をタイムリーに日英できちんと公開することが、沖縄県の今するべき、できる仕事ではないでしょうか。
要請で書いたように、立ち入り調査が実施されても、米軍の裁量で提供される情報が制限され、調査に支障が発生するという事例です。これは、安全、健康、そして枯れ葉剤問題にも関係する問題です。
実質的に意味をなす立ち入り調査とはなにかを明確にし、一つ一つ実をとっていく政策を実行していってもらいたい、 ということで、沖縄県には、上述のような要請をしたということです。
そして、米軍にも奪われた土地への投棄に対して抗議の意思表示を示さなければ、さらに返還予定地への投棄は止むことがないと思います。米軍の原状回復義務がなくとも、意思表示は必要だと思います。それに関しては、宜野湾市に要請をしています。
米軍は確かに汚染源であり、投棄という酷いことをしています。しかし、それに対して本当にきちんとした抗議の意思表示を、適切なタイミングで、伝わる言葉で正式な回路でしているか、ということは考えなければならない。それが沖縄で私たちがやらなければならないことではないか、と思います。
---------------------------------------------
こちらは環境条項などの参考リンクです。
・渉外知事会
日米地位協定の改正についての要請を行っています。
・日本弁護士連合会
日米地位協定に関する意見書 (2014年2月20日)
意見書全文、現行日米地位協定と意見の趣旨との対照表、英語版もあります。
日米地位協定(環境条項)の改正問題に関する会長声明(2015年1月7日)も出しています。
こちらは、2014年10月の日米共同合同発表文書原文です。
英文
沖縄県への要請
この公開されない現場写真については、米軍が公開しない、ということで米軍を非難するのみでなく、沖縄県を動かしていく必要があるということを、沖縄県の環境政策を見ていくNGOとして考えていきたいと思います。
それは、沖縄県が米軍基地への立ち入り調査を要請しているわりには、実際、コトがおこった時に具体的で積極的な姿勢がみえないからです。
宜野湾市への要請書の写しを沖縄県に送る時に、以下のような要請を書きました。
「また、沖縄県におきましては、市への要請でも言及している、米軍の許可がおりないために公開されていない現場写真について、沖縄県が日米政府に要請している「環境条項」の面から取り組んでいただきたいと思います。
本件は、立ち入り調査が実施されても、米軍の裁量で提供される情報が制限され、調査に支障が発生するという問題が炙りだされた事例であると考えます。立ち入り調査が実質的な目的を果たすものとなるよう、沖縄は、要請事項をより明確にし、関係諸機関に働きかけてくださるよう要請いたします。
沖縄県の米軍との情報交換に関しては、沖縄県は「平成 26 年度 第 2 回 米軍施設環境対策事業検討委員会 議事概要」において委員の指摘に対し、「米軍環境部門と情報交換をはじめられるよう、調整していきたい」と見解を述べています。このような具体的な機会を活かし、米軍と恒常的な交渉を行い、沖縄県と米軍の情報交換の回路を構築していくことが必要だと思われます。」
沖縄県と環境条項
環境条項の面からの取り組みとは何か?
沖縄県は、基地への立ち入りや汚染調査に関する、日米地位協定の見直しを要求してきた経緯があります。
沖縄県サイト 「日米地位協定の見直しに関する主な経緯」 (2014年8月14日までの更新)
環境条項が地位協定に含まれていないことが問題視され、軍転協、渉外知事会などでも要請事項となってきました。
特にこの1,2年、政治的な文脈--前県知事の辺野古の埋め立て承認の問題--と絡めて、西普天間の返還、そしてそれに伴う立ち入り調査の件は「基地負担軽減」の一つとして扱われてきました。
2013年10月3日の「日米安全保障協議委員会共同発表「より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて」では、「2013年11月末までに,返還を予定している米軍の施設及び区域への立入りに関する枠組みについての実質的な了解を達成することを決定した。」と発表され、同年10月24日に行われた第2回 駐留軍用地跡地利用推進協議会では仲井真知事(当時)が掘削を伴う返還前の立ち入り調査を要請しています。
この件に関しては、立ち入りの枠組みを決めるための検討が必要であると沖縄BDから要請書を出しています。[返還跡地問題]2+2:立入り調査の枠組みについての要請(2013.11.22)
それが非常に露骨な形で現れたものが、当時の仲井真県知事による辺野古新基地建設のための埋め立て承認の直前、2013年12月に政府に提出した沖縄県の要請書です。2.の基地負担軽減の部分が立ち入り調査などの件が要請事項として記されている部分です。
そもそも、このような調査の権利は、当然あるべき権利としてみなすべきで、その権利を要求することは、「負担軽減」の範疇にいれてはいけないことだと考えます。また、政治的取引の材料として議論されるべき問題でもありません。
その沖縄県要請書はこちら。
この後、2014年6月24日返還前の掘削を伴う埋蔵文化財調査についての日米合意があり、8月15日から、宜野湾市による立入り及び調査が可能となります。(この経緯についてはキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区の汚染調査などに関するこれまでの経緯の記事参照)
そして、この問題は、2014年11月の県知事選前に再び浮上します。10月20日、日米共同合同発表で米軍基地内の環境調査や日本側の立ち入りや環境基準などを定める補足協定を実質合意したと発表します。これは当時の現職、仲井真知事への後押しであると解釈されています。
日本の環境基準維持 基地内調査で合意発表 (沖縄タイムス 2014.10.21)
この合意書全体についての問題は、ここでは言及しませんが、立ち入りに関する原文の該当部分を切り出しておきます。

語彙も非常に曖昧ですし、具体性に欠け、米軍の裁量によって左右されるという問題が解決される保証はないい、ということは明白です。
これに対して、QABニュースでコメントしました。県内紙でも桜井国俊さんや砂川かおりさんがコメントなさっていましたがクリッピングがおぼつかず。

QAB環境協定で実質合意(2014.10.21)
”アメリカ軍基地で環境汚染が発生した場合などに日本側の立ち入りを認める新協定について日米政府は20日、実質合意したと発表しました。しかし、県内の専門家からは疑問の声も上がっています。
20日に開かれた普天間基地負担軽減推進会議で仲井眞知事は「環境補足協定につきましては、日米地位協定から54年を経て、初めての成果であります。新たな枠組みを作られたことは、沖縄を始め、全国の米軍基地所在自治体から高く評価されるものだと思います」と新しい環境協定を高く評価しました。
返還軍用地の汚染が次々と発覚し、嘉手納より南の大規模な土地の返還を控える中、新しい協定では基地内で環境汚染が発生した場合や返還に向けて調査が必要になった場合、日本の関係者の立ち入りを認めることが明記されました。
しかしこの発表について早くも疑問の声が上がっています。沖縄市のドラム缶問題などに取り組んでいる沖縄生物多様性市民ネットワークの河村雅美さんは「評価はできないと思っています。これまでとどこがどう違うのか全くわからないし」と指摘。実はアメリカ軍基地への立ち入りについては今から40年以上前既に合意されていました。
1973年の合意では、県や市町村が現場を直接視察したり、必要と考えた場合にはサンプルを入手することができると書かれています。しかしこの合意事項は2003年まで、その存在自体を沖縄県は知らされず実際制度が活用されていなかったのです。
河村さんは「制度としてはあるんだけど、米軍の裁量で全てが決まってしまう、そういう状態だったというのが現状です。市町村とか沖縄にとって適切なものになっているかどうかが不透明であると、そこが解決されていないんじゃないかという懸念がありますよね」と指摘し、今回もアメリカ軍や日米両政府の裁量に委ねられ、実際には意味のないものにならないかと懸念しています。”
朝日新聞でもコメントしました。
朝日新聞「米軍基地に新環境基準 地位協定補足、自治体調査ルール化へ」(2014年10月21日)
”日米両政府は20日、日米安保条約に基づいて米軍による施設、土地の利用などを定めている「日米地位協定」を補足する新たな協定(環境補足協定)を結ぶことで大筋合意した、と発表した。基地内により厳しい環境基準を適用し、土壌汚染などの事故が起きた際、自治体が立ち入り調査するルールなどを今後定める。
1960年の地位協定には環境保護の規定がなく、仲井真弘多知事ら沖縄県側は、土壌や水質の汚染が指摘されてきた米軍基地内の環境調査を可能にする補足協定をつくるよう求めていた。11月の沖縄県知事選を控え、安倍政権側には、米側との合意を通じて、3選をめざす仲井真氏を後押しする狙いもある。
新協定には、日米双方の環境基準のうち厳しい方を採用した「日本環境管理基準」(JEGS)の適用を明記。在日米軍は95年からJEGSを自主的な規制としてきたが、運用実態は不透明だった。日本側には、明文化によって米側に順守を義務づける狙いがある。
新協定は日本側による米軍基地内の環境調査について、(1)環境事故が起きた際の立ち入り調査(2)基地返還前の現地調査――を盛り込む。これまでは基地内の立ち入りには米側の許可が必要だったが、地元自治体による調査も容易になるという。
岸田文雄外相は「協定の正式署名をできるだけ早期に実現する」と述べ、新協定締結に向けた協議を急ぐ考えを示した。
20日午後に首相官邸で説明を受けた仲井真氏は、記者団に「しっかり使える形で仕上げていただければ。難しいものを頑張られて、高く評価する」と述べた。
一方、基地内の環境汚染問題に取り組む「沖縄・生物多様性市民ネットワーク」の河村雅美ディレクターは、新協定について「実効性があるのか疑問」と指摘した。 (村松真次、山岸一生)”
県政のやるべきことは?
結局、知事選はこの後押しも効力はなかったのか翁長雄志氏が知事選に勝利しました。骨抜きの環境協定は提示されたままの状態で、まだ仕切り直されていません。
翁長県政でこの部分を仕切りなおすことは、嘉手納より南の返還計画とともに「基地負担」の部分を問いなおすこととともにやっていかなければならないことでしょう。
沖縄市サッカー場問題が政治問題として利用されてしまった面があることは忸怩たる思いがありますし、一つ一つ声をあげきれていないことは反省点です。しかし、翁長県政に変わったことをきっかけに具体的に県政に問題提起をしていくことは重要だと思っています。
この間、沖縄県は何をしていたかといえば、2014年度から沖縄県基地環境特別対策室を一括交付金事業として立ち上げています。その中で、米軍施設環境対策事業検討委員会を設置し、”基地返還予定地及び返還跡地における環境問題や在沖米軍の活動に起因する環境問題に対応するため、米軍施設における環境情報の構築と環境対策方針を策定し、国と連携した新たな環境保全のしくみ及び米軍施設とその周辺における環境情報をまとめた環境カルテを作成する予定”しているそうです。
沖縄県HP:米軍施設環境対策事業検討委員会
QAB 米軍施設環境対策事業検討委員会 (2015.2.7)
この会議の中でも、委員から「環境に関する基本的な事項については、米軍との間で情報交換ができるような仕組みを作って欲しい。」という(いまさらの)意見がでています。県の回答は「ご指摘の趣旨を踏まえ、米軍環境部門と情報交換をはじめられるよう、調整していきたい。 」という行政お得意の「調整」回答です。
しかし、現実は元跡地で、返還予定跡地の文化財調査で汚染が発覚しています。実際は現実に起こっている問題で交渉力を鍛えていくこと、米軍との交渉を防衛局任せにせず、日本政府との庇護的・パターナリスティックな関係を断ち切っていくことが県の環境政策には必要であるのではないか、と思います。
写真を出す交渉くらい、カルテとかしくみとか出来上がる前にできるでしょう。そして、これを材料に実質的な内容を伴う環境補足条項の締結を日米に要請し、その要請をタイムリーに日英できちんと公開することが、沖縄県の今するべき、できる仕事ではないでしょうか。
要請で書いたように、立ち入り調査が実施されても、米軍の裁量で提供される情報が制限され、調査に支障が発生するという事例です。これは、安全、健康、そして枯れ葉剤問題にも関係する問題です。
実質的に意味をなす立ち入り調査とはなにかを明確にし、一つ一つ実をとっていく政策を実行していってもらいたい、 ということで、沖縄県には、上述のような要請をしたということです。
そして、米軍にも奪われた土地への投棄に対して抗議の意思表示を示さなければ、さらに返還予定地への投棄は止むことがないと思います。米軍の原状回復義務がなくとも、意思表示は必要だと思います。それに関しては、宜野湾市に要請をしています。
米軍は確かに汚染源であり、投棄という酷いことをしています。しかし、それに対して本当にきちんとした抗議の意思表示を、適切なタイミングで、伝わる言葉で正式な回路でしているか、ということは考えなければならない。それが沖縄で私たちがやらなければならないことではないか、と思います。
---------------------------------------------
こちらは環境条項などの参考リンクです。
・渉外知事会
日米地位協定の改正についての要請を行っています。
・日本弁護士連合会
日米地位協定に関する意見書 (2014年2月20日)
意見書全文、現行日米地位協定と意見の趣旨との対照表、英語版もあります。
日米地位協定(環境条項)の改正問題に関する会長声明(2015年1月7日)も出しています。
こちらは、2014年10月の日米共同合同発表文書原文です。
日米共同合同発表20141020_j by BDOkinawa
英文
Japan-U.S. Joint Press Release20141020 by BDOkinawa
Posted by 沖縄BD at 16:42│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。