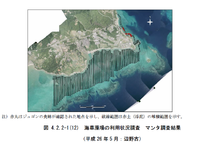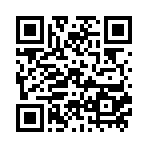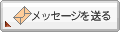沖縄県生物多様性地域戦略策定検討委員会のレポート4
2012年02月25日/ 生物多様性地域戦略
去った2月14日に、第3回目の沖縄県生物多様性地域戦略策定検討委員会が開催されました。「骨子(たたき台)」案の第3稿が事務局(自然保護課)から提出され、第2章の「基本姿勢と目標」に関する議論を中心に委員会は行われました(沖縄県の報告はここをクリック)。
 第3稿に対しての僕の感想は、第1章は修正や改善がなされ、文章としてはある程度充実。これからイラストやコラム等が入っていく予定なので、読み易く、分かり易くなるはず。しかし第2章の部分は、まだ十分に練られておらず、委員会の議論にのせるには少し無理があったのでは、というところです。まあその分、第2章はより基本的な部分から委員会の意見が反映されることになります。(右の写真は河村雅美さんからの提供)
第3稿に対しての僕の感想は、第1章は修正や改善がなされ、文章としてはある程度充実。これからイラストやコラム等が入っていく予定なので、読み易く、分かり易くなるはず。しかし第2章の部分は、まだ十分に練られておらず、委員会の議論にのせるには少し無理があったのでは、というところです。まあその分、第2章はより基本的な部分から委員会の意見が反映されることになります。(右の写真は河村雅美さんからの提供)
さて「基本姿勢と目標」に関する報告は次にゆずるとして、今回僕が取り上げたいのは、沖縄の生物多様性をめぐる「課題」についてです。第1章、第3節「沖縄県の生物多様性について」で「沖縄県の生物多様性の現状と課題」として整理されている部分です。
「沖縄県の生物多様性の現状と課題」
概して「現状と課題」という項目は、現状と課題の実態を記載していると理解されますが、見方をかえれば、作成者(この場合は沖縄県自然保護課)の「現状と課題」に対する認識を示していると理解することもできます。
骨子案の「沖縄県の生物多様性の現状と課題」のなかで、「県全体の課題」として掲げられているのは以下の5つです。
1)人間活動や開発など、人が引き起こす負の要因による問題
2)自然に対する人間の働きかけと関心が減ることによる問題
3)外来種などによる生態系の撹乱のためによる問題
4)地球温暖化に伴う問題
5)基地が存在することによる問題
*第3稿のp16−17の部分です(第3稿はここをクリック)。
基本的には、1〜4は「2010年生物多様性国家戦略」の中で位置づけられており、特に1〜3は「生物多様性の3つの危機」という表現でよく耳にすることがあると思います。また地球温暖化の問題は、島嶼の沖縄にとっては、海水面の上昇やサンゴ礁の白化という形で認識されてきました。そして5は「基地の島・沖縄」ゆえの問題です。
この課題のリストは、ある意味全体をカバーしてはいるのですが、何か「人ごと感」が漂っているような気がして僕は納得していません。僕としては、やはり、環境保全のための既存の制度が機能してこなかったことを課題として、地域戦略のなかで位置づけるべきだと考えています。そしてそれを第1稿の段階から委員会で提起しています。
環境保全のための制度について
沖縄県には、環境保全のための行政の制度が、国、県、地方自治体の各々のレベルで沢山あります。国立公園、国定公園などの自然公園、鳥獣保護区、天然記念物、環境影響評価法や条例、「自然環境の保全に関する指針」で示されているゾーニング等、書き出せばきりがありません。それからコミュニティーレベルにおける文化の一部として、自主ルール的環境保全の仕組みが残っているところもあります。
しかし沖縄の現状を見れば、環境保全の制度がうまく機能していないことは明らかだと思います。
 例えばメディアでよく取り上げられる、泡瀬干潟埋立てや辺野古/大浦湾での米軍基地建設に関する環境アセス。この両方において、環境アセス自体が、環境保全というよりも、事業を進めるための「お墨付き」制度となっていることが指摘されてきました(日本自然保護協会の泡瀬干潟埋立ての環境アセスに対する意見はここをクリック)。
例えばメディアでよく取り上げられる、泡瀬干潟埋立てや辺野古/大浦湾での米軍基地建設に関する環境アセス。この両方において、環境アセス自体が、環境保全というよりも、事業を進めるための「お墨付き」制度となっていることが指摘されてきました(日本自然保護協会の泡瀬干潟埋立ての環境アセスに対する意見はここをクリック)。
(写真は埋立てが進む泡瀬干潟 泡瀬干潟ウミエラ館のHPより)
ただ「辺野古アセス」に関しては、多くの県民や専門家からの批判もあり、日本政府が提出した「評価書」に対して、県知事意見は「環境保全は不可能」という厳しい判断を下しています (知事意見はここをクリック)。この知事意見をもって「制度は機能している」という見方もあるかもしれません。
しかしここまでくるのに、あまりにも時間と労力とお金(アセスには国民の税金86億円が費やされています!)がかかりすぎている。「方法書」の段階ですでに多くの問題は露呈しており、その段階でも環境保全が非常に難しいという判断もできたはずです。また、今回の知事意見がどこまで活かされるのかも分からない状況のなので、今回の知事意見や評価書の段階で住民意見を聞いたという事実だけをもって「アセス制度が機能している」とすることはできないはずです。
それから、沖縄県で行われる事業の多くは、規模が小規模であり、また独立したものと扱われているため、環境保全の制度自体が十分に適用されないという問題もあります。
これは沖縄の海岸線の埋立てや護岸工事や人工ビーチの造成を見ると分かると思います。

上は「貝の渚を歩く貝」の名和純さんが作成した人工ビーチのマップです。
埋立てのマップも名和さんは作成しています。こちらをクリック。
これらは個々の事業としては、それほど環境負荷を生み出さないかもしれません。しかし、他の事業との相乗的関係や全体という視点からみた場合、一つの大規模プロジェクトよりもより大きな環境負荷を生み出しているかもしれません。
また生物の移植や移動が環境負荷の緩和措置として行われますが、それは移植や移動に他に適切な場所があるという前提があってはじめて機能するはずです。しかしその前提さえも成り立たないのが今の沖縄の現状ではないでしょうか。
既存の環境保全の制度の検証について
ではなぜ沖縄県の生物多様性地域戦略の骨子案のなかで、「既存の環境保全の制度」についての議論がなされていないのでしょうか。推測の域を脱しませんが、これまでの流れからいろいろ理由を考えることができます。
まず一番分かり易い理由は、今回の骨子案の基になる22年度の『沖縄県生物多様性地域戦略策定事業〜調査報告書』において、既存の制度についての評価が十分に行われていないということ(報告書はここをクリック)。
この報告書自体は、コンサルが作成しており、コンサルも立場上、既存の行政の制度にいろいろ批判することができないのかもしれません。あるいは制度への視点が、本当に欠如していたのかもしれません。その点はこれから確認をしたいと思います。
次に考えられるのが、「縦割り行政」のなか、一つの課、つまり自然保護課が、他の部局の管轄である制度に対してなかなか意見を言いにくい、というのもあるのかもしれません。
特に生物多様性地域戦略が、時として激しく対立することもある環境保全と経済活動の関係を扱わなければならないことを考えると、その対立が表面化する行政の制度についての検証は、骨子案の時点では避けたのかもしれません。
そして、もかしたらこの制度の問題については、事務局からではなく、委員から提議してもらおうという事務局の戦略なのかもしれません。沖縄BDの吉川(僕です)ぐらいが、すぐ提議してくるだろうと…。まあそれはそれで、戦略としてはとてもいいと思います。
これからの方向性
いずれにしても「既存の環境保全の制度」についての検証を、この地域戦略のなかで位置づけていくことは必要です。実際、この問題については、「具体的に議論していく」「『一般的課題』において規模の小さな事業に対してアセス条例が適用されていない事などを記載する予定としています」という対応方針を事務局からもらっています(検討委員会からの意見への事務局の対応についてはここをクリック)。
僕としても、さすがに「制度が機能していない」ということだけを強調してはなんなので、第3回の委員会では、「機能している制度についても紹介する。機能していないものは課題として取り上げる」という形で再提言をしています。
とにかく、この課題が地域戦略でこれからどのように位置づけられていくのか、特に他の部局との調整・関係も視野にいれて、多くの人々に注目してもらいたいと思います。
それからもう一つ忘れてならないのは、我々市民・住民自体が、環境保全の制度自体をあまり知らなくて、活かせていないという事実です。ある意味「行政におまかせ状態」であることです。
「辺野古アセス」でも象徴されるように、市民・住民が本気で関われば、環境保全の制度を機能させることは可能だと思います。そのためにも、環境保全の仕組みを僕ら市民・住民がいろいろ知り、活用するすべを身につけていくことが必要でしょう。
長くなりましたが、以上です。
吉川秀樹
追記:
 3年前、写真手前のハスノハギリとガジュマルの木々は、「まっすぐ」な歩道を造るために伐採される運命でした。
3年前、写真手前のハスノハギリとガジュマルの木々は、「まっすぐ」な歩道を造るために伐採される運命でした。
しかし、近くにある県の天然記念物のハスノハギリの森とこの木々は一体であると県や名護市に働きかけたところ、県は伐採をしないという判断を下しました。そして造られたのが写真の「廻る歩道」です(写りは地味ですが、、)。
「環境保全の制度は機能するんだ」「歩道をこんな形で造ることも出来るんだ」
嬉しかったです。
 第3稿に対しての僕の感想は、第1章は修正や改善がなされ、文章としてはある程度充実。これからイラストやコラム等が入っていく予定なので、読み易く、分かり易くなるはず。しかし第2章の部分は、まだ十分に練られておらず、委員会の議論にのせるには少し無理があったのでは、というところです。まあその分、第2章はより基本的な部分から委員会の意見が反映されることになります。(右の写真は河村雅美さんからの提供)
第3稿に対しての僕の感想は、第1章は修正や改善がなされ、文章としてはある程度充実。これからイラストやコラム等が入っていく予定なので、読み易く、分かり易くなるはず。しかし第2章の部分は、まだ十分に練られておらず、委員会の議論にのせるには少し無理があったのでは、というところです。まあその分、第2章はより基本的な部分から委員会の意見が反映されることになります。(右の写真は河村雅美さんからの提供)さて「基本姿勢と目標」に関する報告は次にゆずるとして、今回僕が取り上げたいのは、沖縄の生物多様性をめぐる「課題」についてです。第1章、第3節「沖縄県の生物多様性について」で「沖縄県の生物多様性の現状と課題」として整理されている部分です。
「沖縄県の生物多様性の現状と課題」
概して「現状と課題」という項目は、現状と課題の実態を記載していると理解されますが、見方をかえれば、作成者(この場合は沖縄県自然保護課)の「現状と課題」に対する認識を示していると理解することもできます。
骨子案の「沖縄県の生物多様性の現状と課題」のなかで、「県全体の課題」として掲げられているのは以下の5つです。
1)人間活動や開発など、人が引き起こす負の要因による問題
2)自然に対する人間の働きかけと関心が減ることによる問題
3)外来種などによる生態系の撹乱のためによる問題
4)地球温暖化に伴う問題
5)基地が存在することによる問題
*第3稿のp16−17の部分です(第3稿はここをクリック)。
基本的には、1〜4は「2010年生物多様性国家戦略」の中で位置づけられており、特に1〜3は「生物多様性の3つの危機」という表現でよく耳にすることがあると思います。また地球温暖化の問題は、島嶼の沖縄にとっては、海水面の上昇やサンゴ礁の白化という形で認識されてきました。そして5は「基地の島・沖縄」ゆえの問題です。
この課題のリストは、ある意味全体をカバーしてはいるのですが、何か「人ごと感」が漂っているような気がして僕は納得していません。僕としては、やはり、環境保全のための既存の制度が機能してこなかったことを課題として、地域戦略のなかで位置づけるべきだと考えています。そしてそれを第1稿の段階から委員会で提起しています。
環境保全のための制度について
沖縄県には、環境保全のための行政の制度が、国、県、地方自治体の各々のレベルで沢山あります。国立公園、国定公園などの自然公園、鳥獣保護区、天然記念物、環境影響評価法や条例、「自然環境の保全に関する指針」で示されているゾーニング等、書き出せばきりがありません。それからコミュニティーレベルにおける文化の一部として、自主ルール的環境保全の仕組みが残っているところもあります。
しかし沖縄の現状を見れば、環境保全の制度がうまく機能していないことは明らかだと思います。
(写真は埋立てが進む泡瀬干潟 泡瀬干潟ウミエラ館のHPより)
ただ「辺野古アセス」に関しては、多くの県民や専門家からの批判もあり、日本政府が提出した「評価書」に対して、県知事意見は「環境保全は不可能」という厳しい判断を下しています (知事意見はここをクリック)。この知事意見をもって「制度は機能している」という見方もあるかもしれません。
しかしここまでくるのに、あまりにも時間と労力とお金(アセスには国民の税金86億円が費やされています!)がかかりすぎている。「方法書」の段階ですでに多くの問題は露呈しており、その段階でも環境保全が非常に難しいという判断もできたはずです。また、今回の知事意見がどこまで活かされるのかも分からない状況のなので、今回の知事意見や評価書の段階で住民意見を聞いたという事実だけをもって「アセス制度が機能している」とすることはできないはずです。
それから、沖縄県で行われる事業の多くは、規模が小規模であり、また独立したものと扱われているため、環境保全の制度自体が十分に適用されないという問題もあります。
これは沖縄の海岸線の埋立てや護岸工事や人工ビーチの造成を見ると分かると思います。

上は「貝の渚を歩く貝」の名和純さんが作成した人工ビーチのマップです。
埋立てのマップも名和さんは作成しています。こちらをクリック。
これらは個々の事業としては、それほど環境負荷を生み出さないかもしれません。しかし、他の事業との相乗的関係や全体という視点からみた場合、一つの大規模プロジェクトよりもより大きな環境負荷を生み出しているかもしれません。
また生物の移植や移動が環境負荷の緩和措置として行われますが、それは移植や移動に他に適切な場所があるという前提があってはじめて機能するはずです。しかしその前提さえも成り立たないのが今の沖縄の現状ではないでしょうか。
既存の環境保全の制度の検証について
ではなぜ沖縄県の生物多様性地域戦略の骨子案のなかで、「既存の環境保全の制度」についての議論がなされていないのでしょうか。推測の域を脱しませんが、これまでの流れからいろいろ理由を考えることができます。
まず一番分かり易い理由は、今回の骨子案の基になる22年度の『沖縄県生物多様性地域戦略策定事業〜調査報告書』において、既存の制度についての評価が十分に行われていないということ(報告書はここをクリック)。
この報告書自体は、コンサルが作成しており、コンサルも立場上、既存の行政の制度にいろいろ批判することができないのかもしれません。あるいは制度への視点が、本当に欠如していたのかもしれません。その点はこれから確認をしたいと思います。
次に考えられるのが、「縦割り行政」のなか、一つの課、つまり自然保護課が、他の部局の管轄である制度に対してなかなか意見を言いにくい、というのもあるのかもしれません。
特に生物多様性地域戦略が、時として激しく対立することもある環境保全と経済活動の関係を扱わなければならないことを考えると、その対立が表面化する行政の制度についての検証は、骨子案の時点では避けたのかもしれません。
そして、もかしたらこの制度の問題については、事務局からではなく、委員から提議してもらおうという事務局の戦略なのかもしれません。沖縄BDの吉川(僕です)ぐらいが、すぐ提議してくるだろうと…。まあそれはそれで、戦略としてはとてもいいと思います。
これからの方向性
いずれにしても「既存の環境保全の制度」についての検証を、この地域戦略のなかで位置づけていくことは必要です。実際、この問題については、「具体的に議論していく」「『一般的課題』において規模の小さな事業に対してアセス条例が適用されていない事などを記載する予定としています」という対応方針を事務局からもらっています(検討委員会からの意見への事務局の対応についてはここをクリック)。
僕としても、さすがに「制度が機能していない」ということだけを強調してはなんなので、第3回の委員会では、「機能している制度についても紹介する。機能していないものは課題として取り上げる」という形で再提言をしています。
とにかく、この課題が地域戦略でこれからどのように位置づけられていくのか、特に他の部局との調整・関係も視野にいれて、多くの人々に注目してもらいたいと思います。
それからもう一つ忘れてならないのは、我々市民・住民自体が、環境保全の制度自体をあまり知らなくて、活かせていないという事実です。ある意味「行政におまかせ状態」であることです。
「辺野古アセス」でも象徴されるように、市民・住民が本気で関われば、環境保全の制度を機能させることは可能だと思います。そのためにも、環境保全の仕組みを僕ら市民・住民がいろいろ知り、活用するすべを身につけていくことが必要でしょう。
長くなりましたが、以上です。
吉川秀樹
追記:
 3年前、写真手前のハスノハギリとガジュマルの木々は、「まっすぐ」な歩道を造るために伐採される運命でした。
3年前、写真手前のハスノハギリとガジュマルの木々は、「まっすぐ」な歩道を造るために伐採される運命でした。しかし、近くにある県の天然記念物のハスノハギリの森とこの木々は一体であると県や名護市に働きかけたところ、県は伐採をしないという判断を下しました。そして造られたのが写真の「廻る歩道」です(写りは地味ですが、、)。
「環境保全の制度は機能するんだ」「歩道をこんな形で造ることも出来るんだ」
嬉しかったです。
Posted by 沖縄BD at 11:43│Comments(0)