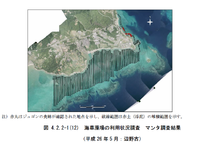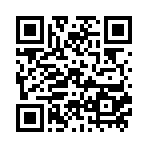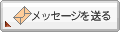第2回沖縄県生物多様性地域戦略策定検討委員会のレポート3
2011年12月24日/ 生物多様性地域戦略
第2回沖縄生物多様性地域戦略レポ3<地域戦略・ABS・沖縄>
で、次のトピックはこれです。
2)「遺伝資源から得られる利益の公正かつ衡平な配分」という目的と沖縄の関係について
第1回策定検討委員会に提出された生物多様性地域戦略の「骨子(たたき台)」(第1稿)への僕の意見の一つは、
たたき台12頁の地域戦略の位置づけについての説明が不十分である。生物多様性条約との関係、他の法や条例との関係が不明確である。その結果、沖縄県地域戦略策定において参考とするべき条約の内容が、骨子案に十分に反映されてなく、日本政府の描く地域戦略のみが前面に反映されてしまっているようにみられる。
でした。
それに対して第2回委員会で事務局が示した「対応方針」は、
地域戦略においても条約の基本理念を踏まえる必要があります。その理念は生物多様性の保全と持続可能な利用と理解しており、地域戦略の基本理念にはそれが反映されていると考えます。
でした。
僕のぶっきらぼうな記述に対して、です・ます調で丁寧に回答してくれていて恐縮しているのですが、それはちょっと置いておいて、事務局の見解と僕の見解のずれについて少し詳しく触れてみたいと思います。
「生物多様性条約の内容が骨子案に十分に反映されてない」と書いた時、僕の頭には次の2つのことがありました。
一つは、生物多様性条約の包括的なアプローチと精神です。つまり狭い意味での「環境」という捉え方ではなく、人々の「命」や「暮らし」を育むものとしての「環境」に目をむけた条約のアプローチと精神です。これは沖縄BDでは、「環境」「平和」「人権」の繋がりということで理解してきました。もう一つは、生物多様性条約の三つの目の目的とされている「遺伝子資源から得られる利益の公正かつ衡平な配分」つまりABS(Access and Benefit Sharing)についてです(EICネットによるABSの説明はこちら)。
1番目のことに関してはまた後で書こうと思いますが、問題はこの2番目ABSについてです。ABSについては、骨子1稿では触れていません。今回提出された第2稿でも、追加してもらった生物多様性条約の目的の記述の部分を除いて言及なしでした。
その一番の理由は、県の地域戦略策定の法的根拠となる「生物多様性基本法」でも、ABSについては明確に言及されていないということに関係していると思います。
条約のABSに関わる部分は、発展途上国や先住民族のために特化されたような扱いになっています。COP10であれだけ議論を重ねて「名古屋議定書」が出されましたが、日本国内の問題として「名古屋議定書」が殆ど議論されていないというのがABSの国内での認識を顕著に示していると思います。あるいは、「保全」と「持続可能な利用」という文言の中で読み取ってくれ、というようなことなのかもしれません(でも読み手が頑張らないといけない基本法はいやですよね。)
しかし沖縄をみると、そのABSの問題が非常にリアリティーをもったものとして見えてくると思います。
亜熱帯の豊かな生物多様性に恵まれ、そこから生じる「利益」の可能性を持つ沖縄。同時に国境海域を持ち、アジアにおける共生を目指し、しかし複雑な権力構造や地政構造に置かれている沖縄。国連では先住民族として認められている沖縄の人々。途上国や先住民族の状況と重なるものがあるのが今の沖縄だと思います。
ちなみに沖縄BDでは、COP10に向けての準備のなかで、岡田さんが中心となってABSと沖縄の関係を議論してきました。そして「名古屋COP10沖縄宣言」にその議論を反映させています(Thanks to 岡田さん、河村さん、桜井先生)。
その繋がりにおいて、今回の委員会では「生物多様性条約の『遺伝資源から得られる利益の公正かつ衡平な配分』の目的については、沖縄の生物多様性地域戦略でどう扱うのですか」という質問を、僕は事務局/県にしてみました。
事務局/県からは、生物多様性地域戦略において「ABSの関係はまだ白紙である」「国家戦略がどう扱うかの議論を通して考えていければ」という答えがかえってきました。また委員長から意見を求められた環境省の委員からは、ABSを地域戦略に入れることに対し「(ABSが)国家間の利益配分の議論からでてきたもので、基本的には難しいかもしれないが、もしそれが地域戦略に取り込めたら画期的なものになる。チャレンジであることは確かであるが、国家レベルのことを制約することなく、具体的な成果につながるかどうは分からない」という答でした。
「また日本政府からの指示待ち?」「政府レベルでしか考えていない」と市民の立場としては突っ込みたくなるのですが、県も国もそれぞれの立場があり、それに基づいた回答ではあったと思います。生物多様性基本法にないことを事務局/県が生物多様性地域戦略の「たたき台」に入れることは、難しいというか、勇気がいることだと思うし、それを国が応援することはなお難しいかもしれません。
でも基本的なところは、沖縄の生物多様性地域戦略が、ABS問題について言及するかどうかですよね。それを沖縄の県民がどう考えるかだと思います。生物多様性を守り、持続可能に利用していくための法や制度であって、法や制度自体を守ろうとして生物多様性が失われ、利用できなくなったらまさに本末転倒。
ちなみに生物資源を扱っている会社で働いている委員からは「本土の会社から、沖縄の生物資源を使う時にどのように使っていいのか分からないという意見がある」「企業が生物資源を利用するのに、沖縄の会社と提携するとか、やはりABSに関わる仕組み作りが必要ではないか」という趣旨の意見がでていました。生物資源を扱っている人々にとっては、沖縄においてのABSの問題は実際の問題なんだというのが、共有された認識ではないかと思います。
それゆえ、ABSを視野にいれた生物多様性地域戦略が策定されるべきだというスタンスを示していくことはとても大切なことだと思います。生物多様性基本法も、生物多様性地域戦略でABSに触れてはいけないと書いてはいないはずです。
沖縄BDがCOP10で提出したポジションペーパーの提言8は、
しかし私たちは、国家/政府は、条約の解釈を制限し、生物多様性条約の実現のための 活動に中央/周辺の関係をつくるものであってはならないと考える。市民はその制約を受けず、条約を自ら解釈し、むしろ条約実現の活動を発信する役割であることを確認することを提唱する。
としています。(河村さんの文章です)
なによりも市民、県民からの声があがることが大切だと思います。ABS問題に関してよいアイデアのある人は、ぜひ提案して下さい。また、他の都道府県や自治体の生物多様性地域戦略のなかで、ABSに言及している部分があればぜひご紹介下さい。よろしくお願いします。
ではひとまず、ここまで。
追記:
第2回沖縄県生物多様性地域戦略策定検討委員会が県庁4階の会議室で終わった後、オブザーバーとして参加した沖縄BDの大城さんは、県庁前広場で行われる、辺野古/大浦湾での米軍基地建設の為の環境アセス評価書の提出を阻止する集まりに向かいました。
沖縄の現実です。生物多様性地域戦略になんらかの期待を持って策定委員会に参加しながらも、基地建設計画ですっかり形骸化させられた環境アセス制度へ抗議をしなければならない。環境アセスの仕組みがちゃんと機能していたなら、アセス評価書の阻止なんて誰も考えないはずです。
でも市民参加というのは、そういうことだと思います。制度を作る過程から、そしてその制度がちゃんと機能しているかどうかのチェックまですべて市民が関わること。いい制度ができたからそれでうまくいくのではなくて、その制度を機能させるにも市民の参加が必要であるということ。
市民運動や環境運動を扱ったテキストにありそうなことを書いてしまいましたが、でもそれを現実に悲しいほど痛感させられている沖縄の現状は、正直言ってしんどいです。
Posted by 沖縄BD at 17:04│Comments(1)
この記事へのコメント
市民参加によってこそうまくいくものですね。貴重な意見参考になりました。
Posted by 石垣金星 at 2011年12月27日 01:54