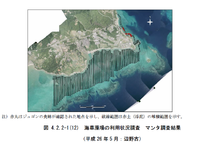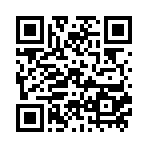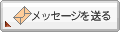県議会陳情:米軍HH60墜落に関する環境調査の件
2014年03月23日/ 議会陳情/ 汚染/ 沖縄県環境政策
昨年8月にキャンプ・ハンセンに墜落したHH-60墜落事故に関する米軍の環境調査が発表されました。
沖縄防衛局サイト HH-60ヘリ墜落事故に係る米側の環境調査結果について(2014.2.18掲載)
発生から半年後という調査結果が米軍から一方的に発表されたこと、また汚染土の除去後に宜野座村の立ち入りを可能とした米軍の対応は大きな問題です。しかし、この間、県の中間報告の要求や、汚染度の処理についての問い合わせをどのように行っていたかわかりません。この県、新聞でもコメントしましたが、やりとりの公開も含め、県に陳情しました。
また、米軍の調査自体も問題があります。池田こみち先生からメディアへ送られたものを暫定コメントとしてご提供いただきましたので、こちらを参考につけ、沖縄県に見解を求めています。
陳情提出後、県の立ち入り調査が許可され3月17日には宜野座村の立ち会いのもと県が土壌のサンプリングを実施したとのこと。しかし、放射線の測定については米軍が認めず、軍側で実施し、25日にも現場を土で埋める作業を始めたいとしているそうです。そちらの記事、リンクもあわせてごらんください。
---------------------------------------
沖縄県議会議長
喜納 昌春殿
昨年8月5日に起きた嘉手納基地所属HH-60ヘリ墜落事故の米軍による環境調査結果が2月18日に発表されました。
発生から半年後に調査結果のみが米軍から一方的に発表されたこと、また汚染土の除去後に宜野座村の立ち入りを可能とした米軍の対応は大きな問題であり、沖縄県としても強く抗議をするべきだと私たちは考えます。
しかし一方で、沖縄県が今回の事故や米軍の環境調査に関する疑問や問題について、沖縄県がどれだけ適切かつ十分な働きかけを米軍に対して行ってきたかも、私たちは知らされておらず、懸念を持っています。
今回の事例を通して、沖縄県が宜野座村とともに問題を洗い出し、解決に向けてねばり強く日米政府と交渉を行っていかなければ、同様の対応がくり返されることが予想されます。そして交渉を継続し、その過程を県民に明らかにし、全県的な問題として県民に認識してもらうことも必要です。
今回の調査について、以下の件を要求します。
1)調査の過程において、米軍の調査結果発表までに、立ち入り許可申請以外に沖縄県が米軍や日本政府にどのように働きかけたのかを明らかにしてください。働きかけを示す文書(調査計画、調査経過過程、汚染土処理計画などの情報や中間報告請求等)なども公表してください。
2) 今回の米軍の調査に関する沖縄県の評価(公表時期、調査方法、米軍と県・宜野座村とのコミュニケーション方法)を公表してください。参考に、専門家によるこの調査の問題点等に関する暫定コメントを添付します。
3) 引き続き、調査の問題について、交渉を継続してください。また、その後の米軍からの説明、今後の米軍や沖縄防衛局との交渉について、その過程をメディアだけでなく、県民にも直接ウェブサイトにアップデイトし、問題認識の共有をはかるようにしてください。
添付:環境総合研究所 池田こみち氏からの暫定コメント
参考:環境総合研究所 池田こみち氏からの暫定コメント
・公表が遅い。明日すべてが終わる段階で公表されても解析する時間すらない。
報告書が非常にわかりにくく、サンプリング場所とサンプル番号と分析結果の対応が整理されていないので、なぜ、何回にも分けて土壌を採取し、いろいろな分析を次々に行っているのか、その理由もわからない。
・土壌採取地点はだれがどのように決めたのか、どのような項目についてどのような順序優先順位で分析することにしたのかなどまったく明らかにされていない。
・調査の対象範囲をどのように決めたのか、影響範囲を1500平米とし、その中のインパクトエリアは50平米に限定しているがその根拠も不明。土壌は表層土壌のみ5回に分けて採取し、分析項目、分析方法も国内法のJIS準拠のものやUSEPA準拠のものもある。
・報告書概要では、金属類についてのみ若干日本の基準を超過しているものがあるとしているが、TPH(Total Petrorium Hydrocarbon)を8検体ほど分析していて高い値がでているにもかかわらず評価を行っていない。
日本の環境省はTPHについて環境基準などの評価尺度をもっていないが、アメリカでは定めている州もある。測定していて数値も幅があり、高い濃度もあるのにそれについては触れていない。燃料が飛散したということの証拠であればそれも記載すべきである。「鉛、ヒ素、カドミウムは航空機の物資であると思われる」とある。
・対象エリアの広さからみて、今回の調査地点数で、面的な汚染の広がりを正しく把握できているかどうか疑問である。すでに除去作業を行って2月19日には完了の予定とある。すべて米側で一方的に決めている。
・TPHについては微生物製材をまいて減少したことを確認した、と書いてあるが、具体的にどの範囲のどの程度の汚染について対策し、結果としてどの程度減少したか、それをどのように確認したか明記されていないので分からないが、結果がどれくらいだと何が問題だからどこまで下げる必要があって、対策を講じたら、どこまでさがったのか、と言う説明がまったくない。
・金属類についても、除去の範囲をどうやって決めたのか、除去作業が十分だったか確認する方法などが示されていない(確認するかどうかも示されていない)ので、十分な対策であるかどうか確認されるかどうか分からない。
また、調査そのものが、分析試料の採取の第三者による立ち会い、分析のクロスチェック(第三者による分析)等が行われていなければ、分析そのものの客観性も確保されているとはいえない。
--------------------------------------------------------------



QAB ニュース: キャンプハンセン 県と村がヘリ墜落現場を立ち入り調査(2014.3.14)


QAB ニュース: 事故から7カ月経過 HH60ヘリ墜落 県や村 現場調査
沖縄防衛局サイト HH-60ヘリ墜落事故に係る米側の環境調査結果について(2014.2.18掲載)
発生から半年後という調査結果が米軍から一方的に発表されたこと、また汚染土の除去後に宜野座村の立ち入りを可能とした米軍の対応は大きな問題です。しかし、この間、県の中間報告の要求や、汚染度の処理についての問い合わせをどのように行っていたかわかりません。この県、新聞でもコメントしましたが、やりとりの公開も含め、県に陳情しました。
また、米軍の調査自体も問題があります。池田こみち先生からメディアへ送られたものを暫定コメントとしてご提供いただきましたので、こちらを参考につけ、沖縄県に見解を求めています。
陳情提出後、県の立ち入り調査が許可され3月17日には宜野座村の立ち会いのもと県が土壌のサンプリングを実施したとのこと。しかし、放射線の測定については米軍が認めず、軍側で実施し、25日にも現場を土で埋める作業を始めたいとしているそうです。そちらの記事、リンクもあわせてごらんください。
---------------------------------------
2014年3月6日
沖縄県議会議長
喜納 昌春殿
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
ディレクター 河村雅美 連絡先070-5482-0084)
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
ディレクター 河村雅美 連絡先070-5482-0084)
キャンプハンセンのHH-60ヘリ墜落事故に係る米軍による環境調査について
昨年8月5日に起きた嘉手納基地所属HH-60ヘリ墜落事故の米軍による環境調査結果が2月18日に発表されました。
発生から半年後に調査結果のみが米軍から一方的に発表されたこと、また汚染土の除去後に宜野座村の立ち入りを可能とした米軍の対応は大きな問題であり、沖縄県としても強く抗議をするべきだと私たちは考えます。
しかし一方で、沖縄県が今回の事故や米軍の環境調査に関する疑問や問題について、沖縄県がどれだけ適切かつ十分な働きかけを米軍に対して行ってきたかも、私たちは知らされておらず、懸念を持っています。
今回の事例を通して、沖縄県が宜野座村とともに問題を洗い出し、解決に向けてねばり強く日米政府と交渉を行っていかなければ、同様の対応がくり返されることが予想されます。そして交渉を継続し、その過程を県民に明らかにし、全県的な問題として県民に認識してもらうことも必要です。
今回の調査について、以下の件を要求します。
1)調査の過程において、米軍の調査結果発表までに、立ち入り許可申請以外に沖縄県が米軍や日本政府にどのように働きかけたのかを明らかにしてください。働きかけを示す文書(調査計画、調査経過過程、汚染土処理計画などの情報や中間報告請求等)なども公表してください。
2) 今回の米軍の調査に関する沖縄県の評価(公表時期、調査方法、米軍と県・宜野座村とのコミュニケーション方法)を公表してください。参考に、専門家によるこの調査の問題点等に関する暫定コメントを添付します。
3) 引き続き、調査の問題について、交渉を継続してください。また、その後の米軍からの説明、今後の米軍や沖縄防衛局との交渉について、その過程をメディアだけでなく、県民にも直接ウェブサイトにアップデイトし、問題認識の共有をはかるようにしてください。
添付:環境総合研究所 池田こみち氏からの暫定コメント
参考:環境総合研究所 池田こみち氏からの暫定コメント
・公表が遅い。明日すべてが終わる段階で公表されても解析する時間すらない。
報告書が非常にわかりにくく、サンプリング場所とサンプル番号と分析結果の対応が整理されていないので、なぜ、何回にも分けて土壌を採取し、いろいろな分析を次々に行っているのか、その理由もわからない。
・土壌採取地点はだれがどのように決めたのか、どのような項目についてどのような順序優先順位で分析することにしたのかなどまったく明らかにされていない。
・調査の対象範囲をどのように決めたのか、影響範囲を1500平米とし、その中のインパクトエリアは50平米に限定しているがその根拠も不明。土壌は表層土壌のみ5回に分けて採取し、分析項目、分析方法も国内法のJIS準拠のものやUSEPA準拠のものもある。
・報告書概要では、金属類についてのみ若干日本の基準を超過しているものがあるとしているが、TPH(Total Petrorium Hydrocarbon)を8検体ほど分析していて高い値がでているにもかかわらず評価を行っていない。
日本の環境省はTPHについて環境基準などの評価尺度をもっていないが、アメリカでは定めている州もある。測定していて数値も幅があり、高い濃度もあるのにそれについては触れていない。燃料が飛散したということの証拠であればそれも記載すべきである。「鉛、ヒ素、カドミウムは航空機の物資であると思われる」とある。
・対象エリアの広さからみて、今回の調査地点数で、面的な汚染の広がりを正しく把握できているかどうか疑問である。すでに除去作業を行って2月19日には完了の予定とある。すべて米側で一方的に決めている。
・TPHについては微生物製材をまいて減少したことを確認した、と書いてあるが、具体的にどの範囲のどの程度の汚染について対策し、結果としてどの程度減少したか、それをどのように確認したか明記されていないので分からないが、結果がどれくらいだと何が問題だからどこまで下げる必要があって、対策を講じたら、どこまでさがったのか、と言う説明がまったくない。
・金属類についても、除去の範囲をどうやって決めたのか、除去作業が十分だったか確認する方法などが示されていない(確認するかどうかも示されていない)ので、十分な対策であるかどうか確認されるかどうか分からない。
また、調査そのものが、分析試料の採取の第三者による立ち会い、分析のクロスチェック(第三者による分析)等が行われていなければ、分析そのものの客観性も確保されているとはいえない。
--------------------------------------------------------------



QAB ニュース: キャンプハンセン 県と村がヘリ墜落現場を立ち入り調査(2014.3.14)


QAB ニュース: 事故から7カ月経過 HH60ヘリ墜落 県や村 現場調査
"2014年8月、宜野座村のキャンプハンセンにHH60ヘリが墜落した事故で、事故から7カ月あまり経過した17日、県や宜野座村は初めて現場の立ち入り調査を実施しました。
県や宜野座村、それに沖縄防衛局や外務省の担当職員ら14人は、17日午前、アメリカ軍立会いのもと立ち入り調査を実施しました。
県やアメリカ軍はそれぞれ、墜落現場の10地点から土壌を採取、およそ1カ月かけてヒ素や重金属など21項目について検査する予定ですが、放射線測定についてはアメリカ軍側が実施したものの県側が実施することを認めなかったということです。
県環境生活部環境保全課の渡嘉敷彰班長は「時間がかかりすぎてると思いますね。もう7カ月経ってるんで。我々もずっと出来るだけ早く調査をしたいという要請をしてたんですけどその結果、今回しか調査できなかった。サンプリングできなかった」と調査後に話していました。
アメリカ軍の調査では環境基準値を大幅に超える鉛やヒ素が検出されていますが、アメリカ軍は、今月25日にも現場を土で埋める作業を始めたいとしていてさらに反発が予想されます。"
Posted by 沖縄BD at 22:57│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。