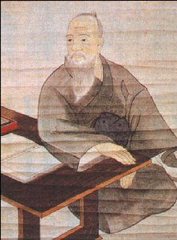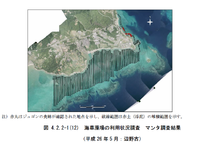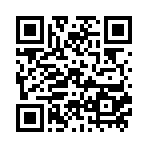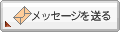「沖縄県環境影響評価条例の改正の骨子案」へのパブコメ
2011年08月31日/ パブコメ
「沖縄県環境影響評価条例の改正の骨子案」へのパブリック・コメントを出しました。

→募集についての沖縄BDの記事はこちら
沖縄で実施されたアセスの問題事例は、新石垣空港、辺野古新基地建設、高江ヘリパッド建設、泡瀬干潟埋立など、枚挙に遑がありません。
今回のパブコメのポイントは
-上=国へ倣えの改正であってはならない。
-この「骨子案」へのパブコメのみで、条例改正に関わる県民意見の聴取としてはならない。これまでの事例を検証し、「条例施行規則」「沖縄県環境影響評価技術指針」の手続きも、県民意見を聞く機会を設けるべきである。
-コミュニケーションの双方向性をより考えていただきたい。「形だけの応答」だけでない、「意味ある応答」がなされる場の設定を、考えてもらいたい(原科幸彦『環境アセスメントとは何か』(2011年、岩波新書、参考)。
-「環境影響評価法の一部を改正する法律」の第52条第3項(未施行)に対応する形で、「沖縄県環境影響評価条例」においても適用除外の拡大を可能にする条項が今後設置されるものと考えられる。そしてこの条項による適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地を適用してはならない。
これについては別記事を設けます。
この点は、国のアセス改正でも注意です→こちら 9/7〆切。
----------------------------------------------------------------------
沖縄・生物多様性市民ネットワーク 文責 吉川秀樹 河村雅美
今回、沖縄県環境影響評価条例(以下アセス条例)が改正されることになり、「沖縄県環境影響評価条例の改正の骨子案」(以下骨子案)に改正の6項目が提示された。1)電子縦覧の義務化や、方法書段階においての説明会開催の義務化など、同条例に対してこれまで沖縄県民が要求してきた事が反映されていること、2)新たなエネルギー政策への動きを受け、風力発電所を対象事業にするとしていること、3)戦略的環境アセス(SEA)に向けての動きとして計画的段階配慮書の手続きが創出されるなど、全体の流れとしては歓迎されるべきであると考える。
しかしこの骨子案からは、今回のアセス条例への改正への取組みが、平成23年4月27日の環境影響評価法の一部改正を受けた、またしても「右(上=国)へ倣え」的な改正に終わり、沖縄県のサンゴ礁を含む、脆弱な島嶼生態系や、狭い範囲における豊かな生物多様性の保全・保護には繋がらない改正になるのではないかという懸念を持たざるをえない。国の法律の整合性のみの観点からではなく、地域に即した条例改正という観点をもった改正としなければならないことを、強く自覚してもらいたい。
沖縄県内でこれまで行われてきた環境アセスは、アセス法に基づくもの、アセス条例に基づくものの両方において、様々な意見を取り入れ、環境保全の観点からよりよい事業を行うという本来の目的を果たせないものがあまりにも多い。
これまでのアセス調査の科学的妥当性(専門家の匿名を含む)や、情報開示/隠蔽の問題、ゼロ・オプション(事業を実施しない選択)がないなど、アセスが成立する基盤に関わる問題がないがしろにされるかたちで行われてきた。そのため、市民・住民の反対運動が続き、また訴訟にまで発展し事業が行われていないことは、まさに現状のアセス条例がきちんと機能していないことを示している。「アセス法の趣旨を没却しかねない」と判じられた新石垣空港アセス、手続きの違法性が訴訟となっている「普天間飛行場代替施設」アセス(いわゆる「辺野古」アセス)はその代表的なものである。
条例の改正には、まず同アセス条例が現在抱えている問題をきちんと整理・検証することが必要であり、それが「沖縄県環境影響評価条例改正の必要性について」で明記され、今回の「骨子案」には勿論、改正全体に反映されることが最優先されるべきだと考える。
また、電子縦覧の義務化という情報提供の部分だけでなく、コミュニケーションの双方向性をより考えていただきたい。「形だけの応答」だけでない、「意味ある応答」がなされる場の設定を、考えてもらいたい。全ての手続きに、公聴会のような場を設けるべきである。
以下、沖縄の生物多様性豊かな自然環境を保護・保全し、未来世代が持続的に自然の恵みの恩恵を受けることができるようにという観点から、まず「骨子案」と「条例改正の流れ」に対して具体的なコメントを提案を行う。そして沖縄におけるアセスの現状を踏まえて「条例の改正」に向けて、現在のアセス条例に関する、具体的なコメントと提案を行う。私たちのコメントと提案を真摯に受け止め、条例改正に反映させて頂きたい。
1)「沖縄県環境影響評価条例の改正の流れ」を見れば、「骨子案」に対してパブリックコメントが位置づけられ明記されており、今回のパブリックコメントに至っている。しかし、より実質的な意味を持つ「改正条例案」に対しては、パブリックコメントの位置づけがなされていない。「骨子案」だけのパブリックコメントでは不十分であり、より具体的なパブリックコメントや議論は、「改正条例案」に対して行われるはずであり、「改正条例案」についてのパブリックコメントを「改正の流れ」のなかできちんと位置づけ、明記し、募集し、反映して頂きたい。「条例施行規則」「沖縄県環境影響評価技術指針」についても、住民意見募集の機会、できればパブリックコメントだけでなく、双方向のコミュニケーションの場を設けることが必要である。この「骨子案」のパブリックコメントのみで、条例改正全体の住民意見を聴取したことにはしないでいただきたい。
2)風力発電所が対象事業となっているが、対象規模等の重要な項目については、骨子案では、まだ明確に示されていない。しかし「沖縄県環境影響評価条例の改正の流れ」を見る限りでは、対象規模等の重要項目についての議論や決定が、「沖縄県環境審議会」や「事業部局等」のみで行われるのではないかという懸念をもつ。1)のコメントと関連するが、風力発電所に関わる対象規模やその他重要事項に関して、どのような手続きを経て決定されるのか、パブリックコメントはどのように位置づけられるのかを明示して頂きたい。
3)「計画段階配慮書の手続の創設」は歓迎され、その目的も理解ができるが、地域の環境特性に照らして、事業そのものを行うべきであるかがまず判断されるべきであると考える。計画段階における「ゼロオプション」を明記して頂きたい。また、配慮書も、制度の趣旨からいえば、電子縦覧を義務化するべきである。
4)「計画段階配慮書の手続きの創設」においては、「配慮手続の実施期間は、条例対象事業の計画の立案の段階」となっていているが、それが守られることが非常に重要である。しかし「事業段階」に近い段階で、「配慮書」が作成・提出され、そのまま「方法書」段階へのアセス手続きに移行していくという事例がこれまでにある。また「特例環境配慮書」が提出された場合、配慮書事体が、本来のアセス手続きの「方法書」「準備書」「評価書」の代用として使用される可能性も否定できない。このような懸念を骨子において明示し、「計画段階配慮書」の役割と手続きと、従来のアセス手続き(方法書、準備書、評価書)の役割と手続きを、相互関係性を保ちながら明確に分けることを明文化して頂きたい。
5)同骨子案には記されてないが、「環境影響評価法の一部を改正する法律」の第52条第3項(未施行)に対応する形で、「沖縄県環境影響評価条例」においても適用除外の拡大を可能にする条項が今後設置されるものと考えられる。そしてこの条項による適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地が含められることを非常に懸念している。辺野古/大浦湾での米軍基地建設ややんばる高江におけるヘリ/オスプレイパッド建設でも分かるように、沖縄における米軍基地建設計画事業や基地の運用は、沖縄の環境に多大な影響を与え、環境の保全、生命の安全の観点からも非常に重要な問題である。それゆえ、決して十分なアセス法やアセス条例とは言えないが、多くの市民・住民が環境アセス法やアセス条例に真摯に関わりながら、環境を守ってきている。軍事基地が適用除外事業に含められると、市民・住民が軍事基地の存在や運用から自然環境、生活環境を守っていく重要な法的手段を奪うことになる。適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地を含めてはいけない。
6)同骨子案では、ここ10年の間に策定・施行されてきた、あるいは現在策定されている関連制度への言及がない。例えば、沖縄県が策定し、「自然環境の保全・再生・適正利用」を達成されるべき最優先項目の一つとして掲げる「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や、戦略的環境アセスを推進する「生物多様性基本法」、そしてその「生物多様性基本法」に基づき沖縄県が策定している「生物多様性地域戦略」との関連性や整合性は重要なはずであるが、同骨子案を読む限りではそれが分からない。少なくとも「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や「生物多様性基本法」「生物多様性地域戦略」との関連性や整合性について明記して頂きたい。また、縦割りを超え、自然保護課など他部署との連携も含め、条例改正にあたってもらいたい。
7)条例の改正には、まず同アセス条例が現在抱えている問題をきちんと整理・検証することが必要であり、それが今回の改正に反映されることが最優先されるべきだと考える。これについては、繰り返しになるが、別途意見募集を行うべきである。ここでは、以下、具体的なコメントと提案を記する。
○ 環境影響評価手続きの透明性を確保するためには徹底した情報公開が必要である。事業者が専門家や有識者の知見を活用する場合は、その氏名・経歴・業績 などを公表すべきである。
○方法書は事業の計画が具体的になり、環境への影響が科学的に正確に評価出来る様な条件が整った段階で提出されるべきものであり、この内容を実質的に満たしていないものは方法書等の文書の要件を満たしているとは考えられない。従って受付そのものを却下する事が出来る事を明文化し、またその事について環境影響評価審査会や専門家等から意見を聴取する事ができるものとする。
○調査、予測および評価の手法等について、計画の変更について事業者側の自由度が高すぎる現行の制度を改め、事業の規模や位置などの要件のみならず、環境への影響が懸念される事項の変更については全て調査段階からのやり直しを義務化することにより、「後出し」によって住民からの反対意見からの抜け道となる事を防ぐ手だてを新たに講じること。
○ これまでの説明会が事業者の計画を一方的に説明する場に成っていて、住民の意見による計画の変更の余地がほとんどない様な形であるのを改め、計画の初期段階から事業実施そのものの可否からゼロベースで検討出来る公聴会を実施すべき事を条例に盛り込むこと。
○道路の計画にあたっては、一連の道路を細かく区切って計画する事で環境影響評価の対象から外す様な手法がこれまで沖縄本島北部のやんばるの林道や西表の林道でも採られており、多くの林道建設が環境影響評価法と条例の対象外とされて法令に基づく環境影響評価がなされないまま建設が実施されて来ているが、これを改めるため、実質的に一連の道路であるかどうかを環境影響評価の観点から科学的に判断し、単に個別の道路計画の幅員や長さのみで形式的に判断はしない形の運用とすること。またその事を実質的に担保出来るように条例および沖縄県環境影響評価技術指針で必要な改正、改訂を行うこと。
○高江における米軍ヘリパッド建設でも示された通り、 ヘリパッドを環境影響評価の対象としないのは合理的でないので、航空機等の離発着を想定する施設は全て法ないし条例の環境影響評価の対象とするように改めること。
○ 施設の運用開始後であっても航空機などの機種の変更等、環境影響の変更が予想される場合にはその事についても環境影響評価の対象とする様に明文化すること。
○現行の環境影響評価法及び条例には罰則規定がなく、事業者が、自らに都合の悪い意見や情報を隠蔽し、改竄してもそれを止める手段がないことは大きな欠陥である。法及び条例の精神である合意形成を著しく阻害する行為に対する罰則 規定や、環境影響評価手続きに係わる不服申し立て・争訟手続きは、国際的潮流も参考にし、早急に確立すること。

→募集についての沖縄BDの記事はこちら
沖縄で実施されたアセスの問題事例は、新石垣空港、辺野古新基地建設、高江ヘリパッド建設、泡瀬干潟埋立など、枚挙に遑がありません。
今回のパブコメのポイントは
-上=国へ倣えの改正であってはならない。
-この「骨子案」へのパブコメのみで、条例改正に関わる県民意見の聴取としてはならない。これまでの事例を検証し、「条例施行規則」「沖縄県環境影響評価技術指針」の手続きも、県民意見を聞く機会を設けるべきである。
-コミュニケーションの双方向性をより考えていただきたい。「形だけの応答」だけでない、「意味ある応答」がなされる場の設定を、考えてもらいたい(原科幸彦『環境アセスメントとは何か』(2011年、岩波新書、参考)。
-「環境影響評価法の一部を改正する法律」の第52条第3項(未施行)に対応する形で、「沖縄県環境影響評価条例」においても適用除外の拡大を可能にする条項が今後設置されるものと考えられる。そしてこの条項による適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地を適用してはならない。
これについては別記事を設けます。
この点は、国のアセス改正でも注意です→こちら 9/7〆切。
----------------------------------------------------------------------
2012年8月31日
「沖縄県環境影響評価条例の改正の骨子案」に対する意見書
沖縄・生物多様性市民ネットワーク 文責 吉川秀樹 河村雅美
今回、沖縄県環境影響評価条例(以下アセス条例)が改正されることになり、「沖縄県環境影響評価条例の改正の骨子案」(以下骨子案)に改正の6項目が提示された。1)電子縦覧の義務化や、方法書段階においての説明会開催の義務化など、同条例に対してこれまで沖縄県民が要求してきた事が反映されていること、2)新たなエネルギー政策への動きを受け、風力発電所を対象事業にするとしていること、3)戦略的環境アセス(SEA)に向けての動きとして計画的段階配慮書の手続きが創出されるなど、全体の流れとしては歓迎されるべきであると考える。
しかしこの骨子案からは、今回のアセス条例への改正への取組みが、平成23年4月27日の環境影響評価法の一部改正を受けた、またしても「右(上=国)へ倣え」的な改正に終わり、沖縄県のサンゴ礁を含む、脆弱な島嶼生態系や、狭い範囲における豊かな生物多様性の保全・保護には繋がらない改正になるのではないかという懸念を持たざるをえない。国の法律の整合性のみの観点からではなく、地域に即した条例改正という観点をもった改正としなければならないことを、強く自覚してもらいたい。
沖縄県内でこれまで行われてきた環境アセスは、アセス法に基づくもの、アセス条例に基づくものの両方において、様々な意見を取り入れ、環境保全の観点からよりよい事業を行うという本来の目的を果たせないものがあまりにも多い。
これまでのアセス調査の科学的妥当性(専門家の匿名を含む)や、情報開示/隠蔽の問題、ゼロ・オプション(事業を実施しない選択)がないなど、アセスが成立する基盤に関わる問題がないがしろにされるかたちで行われてきた。そのため、市民・住民の反対運動が続き、また訴訟にまで発展し事業が行われていないことは、まさに現状のアセス条例がきちんと機能していないことを示している。「アセス法の趣旨を没却しかねない」と判じられた新石垣空港アセス、手続きの違法性が訴訟となっている「普天間飛行場代替施設」アセス(いわゆる「辺野古」アセス)はその代表的なものである。
条例の改正には、まず同アセス条例が現在抱えている問題をきちんと整理・検証することが必要であり、それが「沖縄県環境影響評価条例改正の必要性について」で明記され、今回の「骨子案」には勿論、改正全体に反映されることが最優先されるべきだと考える。
また、電子縦覧の義務化という情報提供の部分だけでなく、コミュニケーションの双方向性をより考えていただきたい。「形だけの応答」だけでない、「意味ある応答」がなされる場の設定を、考えてもらいたい。全ての手続きに、公聴会のような場を設けるべきである。
以下、沖縄の生物多様性豊かな自然環境を保護・保全し、未来世代が持続的に自然の恵みの恩恵を受けることができるようにという観点から、まず「骨子案」と「条例改正の流れ」に対して具体的なコメントを提案を行う。そして沖縄におけるアセスの現状を踏まえて「条例の改正」に向けて、現在のアセス条例に関する、具体的なコメントと提案を行う。私たちのコメントと提案を真摯に受け止め、条例改正に反映させて頂きたい。
1)「沖縄県環境影響評価条例の改正の流れ」を見れば、「骨子案」に対してパブリックコメントが位置づけられ明記されており、今回のパブリックコメントに至っている。しかし、より実質的な意味を持つ「改正条例案」に対しては、パブリックコメントの位置づけがなされていない。「骨子案」だけのパブリックコメントでは不十分であり、より具体的なパブリックコメントや議論は、「改正条例案」に対して行われるはずであり、「改正条例案」についてのパブリックコメントを「改正の流れ」のなかできちんと位置づけ、明記し、募集し、反映して頂きたい。「条例施行規則」「沖縄県環境影響評価技術指針」についても、住民意見募集の機会、できればパブリックコメントだけでなく、双方向のコミュニケーションの場を設けることが必要である。この「骨子案」のパブリックコメントのみで、条例改正全体の住民意見を聴取したことにはしないでいただきたい。
2)風力発電所が対象事業となっているが、対象規模等の重要な項目については、骨子案では、まだ明確に示されていない。しかし「沖縄県環境影響評価条例の改正の流れ」を見る限りでは、対象規模等の重要項目についての議論や決定が、「沖縄県環境審議会」や「事業部局等」のみで行われるのではないかという懸念をもつ。1)のコメントと関連するが、風力発電所に関わる対象規模やその他重要事項に関して、どのような手続きを経て決定されるのか、パブリックコメントはどのように位置づけられるのかを明示して頂きたい。
3)「計画段階配慮書の手続の創設」は歓迎され、その目的も理解ができるが、地域の環境特性に照らして、事業そのものを行うべきであるかがまず判断されるべきであると考える。計画段階における「ゼロオプション」を明記して頂きたい。また、配慮書も、制度の趣旨からいえば、電子縦覧を義務化するべきである。
4)「計画段階配慮書の手続きの創設」においては、「配慮手続の実施期間は、条例対象事業の計画の立案の段階」となっていているが、それが守られることが非常に重要である。しかし「事業段階」に近い段階で、「配慮書」が作成・提出され、そのまま「方法書」段階へのアセス手続きに移行していくという事例がこれまでにある。また「特例環境配慮書」が提出された場合、配慮書事体が、本来のアセス手続きの「方法書」「準備書」「評価書」の代用として使用される可能性も否定できない。このような懸念を骨子において明示し、「計画段階配慮書」の役割と手続きと、従来のアセス手続き(方法書、準備書、評価書)の役割と手続きを、相互関係性を保ちながら明確に分けることを明文化して頂きたい。
5)同骨子案には記されてないが、「環境影響評価法の一部を改正する法律」の第52条第3項(未施行)に対応する形で、「沖縄県環境影響評価条例」においても適用除外の拡大を可能にする条項が今後設置されるものと考えられる。そしてこの条項による適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地が含められることを非常に懸念している。辺野古/大浦湾での米軍基地建設ややんばる高江におけるヘリ/オスプレイパッド建設でも分かるように、沖縄における米軍基地建設計画事業や基地の運用は、沖縄の環境に多大な影響を与え、環境の保全、生命の安全の観点からも非常に重要な問題である。それゆえ、決して十分なアセス法やアセス条例とは言えないが、多くの市民・住民が環境アセス法やアセス条例に真摯に関わりながら、環境を守ってきている。軍事基地が適用除外事業に含められると、市民・住民が軍事基地の存在や運用から自然環境、生活環境を守っていく重要な法的手段を奪うことになる。適用除外事業に米軍基地や自衛隊基地を含めてはいけない。
6)同骨子案では、ここ10年の間に策定・施行されてきた、あるいは現在策定されている関連制度への言及がない。例えば、沖縄県が策定し、「自然環境の保全・再生・適正利用」を達成されるべき最優先項目の一つとして掲げる「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や、戦略的環境アセスを推進する「生物多様性基本法」、そしてその「生物多様性基本法」に基づき沖縄県が策定している「生物多様性地域戦略」との関連性や整合性は重要なはずであるが、同骨子案を読む限りではそれが分からない。少なくとも「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や「生物多様性基本法」「生物多様性地域戦略」との関連性や整合性について明記して頂きたい。また、縦割りを超え、自然保護課など他部署との連携も含め、条例改正にあたってもらいたい。
7)条例の改正には、まず同アセス条例が現在抱えている問題をきちんと整理・検証することが必要であり、それが今回の改正に反映されることが最優先されるべきだと考える。これについては、繰り返しになるが、別途意見募集を行うべきである。ここでは、以下、具体的なコメントと提案を記する。
○ 環境影響評価手続きの透明性を確保するためには徹底した情報公開が必要である。事業者が専門家や有識者の知見を活用する場合は、その氏名・経歴・業績 などを公表すべきである。
○方法書は事業の計画が具体的になり、環境への影響が科学的に正確に評価出来る様な条件が整った段階で提出されるべきものであり、この内容を実質的に満たしていないものは方法書等の文書の要件を満たしているとは考えられない。従って受付そのものを却下する事が出来る事を明文化し、またその事について環境影響評価審査会や専門家等から意見を聴取する事ができるものとする。
○調査、予測および評価の手法等について、計画の変更について事業者側の自由度が高すぎる現行の制度を改め、事業の規模や位置などの要件のみならず、環境への影響が懸念される事項の変更については全て調査段階からのやり直しを義務化することにより、「後出し」によって住民からの反対意見からの抜け道となる事を防ぐ手だてを新たに講じること。
○ これまでの説明会が事業者の計画を一方的に説明する場に成っていて、住民の意見による計画の変更の余地がほとんどない様な形であるのを改め、計画の初期段階から事業実施そのものの可否からゼロベースで検討出来る公聴会を実施すべき事を条例に盛り込むこと。
○道路の計画にあたっては、一連の道路を細かく区切って計画する事で環境影響評価の対象から外す様な手法がこれまで沖縄本島北部のやんばるの林道や西表の林道でも採られており、多くの林道建設が環境影響評価法と条例の対象外とされて法令に基づく環境影響評価がなされないまま建設が実施されて来ているが、これを改めるため、実質的に一連の道路であるかどうかを環境影響評価の観点から科学的に判断し、単に個別の道路計画の幅員や長さのみで形式的に判断はしない形の運用とすること。またその事を実質的に担保出来るように条例および沖縄県環境影響評価技術指針で必要な改正、改訂を行うこと。
○高江における米軍ヘリパッド建設でも示された通り、 ヘリパッドを環境影響評価の対象としないのは合理的でないので、航空機等の離発着を想定する施設は全て法ないし条例の環境影響評価の対象とするように改めること。
○ 施設の運用開始後であっても航空機などの機種の変更等、環境影響の変更が予想される場合にはその事についても環境影響評価の対象とする様に明文化すること。
○現行の環境影響評価法及び条例には罰則規定がなく、事業者が、自らに都合の悪い意見や情報を隠蔽し、改竄してもそれを止める手段がないことは大きな欠陥である。法及び条例の精神である合意形成を著しく阻害する行為に対する罰則 規定や、環境影響評価手続きに係わる不服申し立て・争訟手続きは、国際的潮流も参考にし、早急に確立すること。
Posted by 沖縄BD at 22:58│Comments(0)