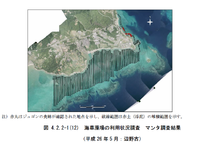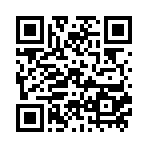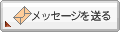第5回生物多様性地域戦略策定検討委員会の開催
2012年10月10日
沖縄県が策定している「生物多様性地域戦略」についてのお知らせです。
来る10月12日(金)に以下の日程で、県の生物多様性地域戦略の骨子案(原案)を策定するための、第5回策定検討委員会が開催されます。同委員会の開催はこれが最後となる予定です。
○第5回策定検討委員会
時間 2012年10月12日(金)14時〜17時
場所 チュラ琉球 7階
委員会はオープンで、オブザーバーとして誰でも参加できますので、関心のある方はぜひご参加下さい。
約一年間かけて、地域戦略の骨子案を練ってきました。
沖縄BDからもNGOとして参加させてもらっていますが、他のNGOやいろいろな人からのアドバイスや提案を頂いて、委員会に臨んできました。アドバイスや提案を頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
今回の委員会では骨子案の5稿目が検討されます。
第1稿から比べると、かなり前進。しかし、まだまだ改善の余地多し、だと思います。
県の自然保護課の第4回目委員会の配布資料欄にこれまでの資料があがっています。→こちら
今後の流れですが、まず策定検討委員会が提出する「骨子案(原案)」が、沖縄県の関係部署による「庁内会議」にかけられ、その後「パブコメ」の手続きにはいります。
そして県の「幹事会」や「庁内会議」を経て、パブコメ+庁内会議の意見を反映させる形で「戦略案」が完成します。
その後「戦略案」が「審議会」を3回経て、沖縄県の生物多様性地域戦略が完成するという流れになります。
「骨子案(原案)」→パブコメ→幹事会・庁内会議→「戦略案」→審議会(3回)→「地域戦略」完成
11月にはパブコメが予定されていますので、どんどん意見を出して、よい地域戦略を作っていきましょう。
以下「続きを読む」で、第4稿について沖縄BDから出した意見の一部を紹介します。
来る10月12日(金)に以下の日程で、県の生物多様性地域戦略の骨子案(原案)を策定するための、第5回策定検討委員会が開催されます。同委員会の開催はこれが最後となる予定です。
○第5回策定検討委員会
時間 2012年10月12日(金)14時〜17時
場所 チュラ琉球 7階
委員会はオープンで、オブザーバーとして誰でも参加できますので、関心のある方はぜひご参加下さい。
約一年間かけて、地域戦略の骨子案を練ってきました。
沖縄BDからもNGOとして参加させてもらっていますが、他のNGOやいろいろな人からのアドバイスや提案を頂いて、委員会に臨んできました。アドバイスや提案を頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
今回の委員会では骨子案の5稿目が検討されます。
第1稿から比べると、かなり前進。しかし、まだまだ改善の余地多し、だと思います。
県の自然保護課の第4回目委員会の配布資料欄にこれまでの資料があがっています。→こちら
今後の流れですが、まず策定検討委員会が提出する「骨子案(原案)」が、沖縄県の関係部署による「庁内会議」にかけられ、その後「パブコメ」の手続きにはいります。
そして県の「幹事会」や「庁内会議」を経て、パブコメ+庁内会議の意見を反映させる形で「戦略案」が完成します。
その後「戦略案」が「審議会」を3回経て、沖縄県の生物多様性地域戦略が完成するという流れになります。
「骨子案(原案)」→パブコメ→幹事会・庁内会議→「戦略案」→審議会(3回)→「地域戦略」完成
11月にはパブコメが予定されていますので、どんどん意見を出して、よい地域戦略を作っていきましょう。
以下「続きを読む」で、第4稿について沖縄BDから出した意見の一部を紹介します。
生物多様性おきなわ戦略への意見と提案
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
吉川秀樹
以下、「生物多様性おきなわ戦略(仮)」第4稿への意見と提案を述べます。なお私がこれまで、第1稿〜3.5稿について提出した意見の中で、その対応が「継続」となっているものについては基本的に省略しますが、これまでの意見がより具体的に反映されるであろうと考える箇所においては再度、意見/提案を述べています。
原文箇所:p22 (1)—2課題
「米軍基地の問題への対応」
意見:北部圏域の米軍基地/演習場の問題を考慮して、もう少し具体的な記述が必要だと考える。
提案:「米軍基地における環境問題へのJapan Environmental Governing Standards「日本環境管理基準」の実質的適用と米軍との協力体制 の欠如」とういう趣旨の文言を入れる。
原文箇所:p25 (2)-2課題
意見:中南部圏域の課題においても米軍基地問題についての言及が必要ではないか。
理由:中南部には返還予定の米軍基地があり、返還、跡地利用の際の汚染除去や自然環境回復や再生の課題がある。
提案:「返還予定の米軍基地の汚染除去や自然環境の回復や再生」という趣旨の文言を入れる。
原文箇所:p36 2 望ましい地域のイメージ (1)北部圏域
意見:海についての記述が少ない。サンゴ以外の海洋生物に対する言及が必要だと考える。ワークショップがやんばるの森で開かれ、その時の議論は、やんばるの森で開かれたこともあり森林関係に集中していたが、それが北部圏域の「望ましい地域のイメージ」の記述に反映しているのではないか。
提案1: 「ジュゴンやウミガメのような貴重種の保全が行われている」という趣旨の文言をいれる。
理由:生物多様性国家戦略においても「豊かな生命を育む沿岸域は、多様で豊富な魚介類を持続的に供給するとともに、北の海ではアザラシが、南の海ではジュゴンが泳ぐ姿が見られるなど、人間と自然の共生のもとに健全な生態系を保っている」とあり、現在日本において、唯一ジュゴンが棲息し、その保護の活動が行われてきた北部圏域の「望ましい地域のイメージ」でも、言及されるべきだと考える。
提2:「海や川の保全が、エコツアーリズムと連携して行われている」という趣旨の文言をいれる。
理由:実際の海や川の保全の取組みが、エコツーリズムと連携して行われ始めており、それは大切であると考える。
原文箇所: p41 2短期目標(2022年(10年)
「生物多様性を保全・再生し、生物多様性の恵みを継続的に享受する」
意見: これは生物多様性地域戦略の全体的な目標と殆ど同じであり、短期目標としては分かりにくい。
提案:「生物多様性を保全・再生し、生物多様性の恵みを継続的に享受する制度基盤を確立する。」という趣旨の文言にする。
原文箇所:p42 3 社会経済的仕組みの考慮
「生物多様性を保全することが経済的な負担となるのではなく、保全することが付加価値となって経済的に有利となる仕組みを検討する。」
提案:「保全(活動)を新たなる公共の事業の仕組みに位置づけることを検討する」といった趣旨の文言を加えてはどうか。
理由:保全により付加価値を生み出すことは時間がかかる場合が多い。むしろ保全(活動)自体を、縮小されていく公共工事に変わる公共事業としての経済活動とすることがまず必要だと考える。
原文箇所:p43 第5節 基本戦略
提案: 6として「上記の基本戦略を進めるための財源の確保と適切な運用を図る」という趣旨の文言を加える。
理由:地域戦略において、財源へ確保と運用についての言及は不可欠だと考える。
原文箇所:p44 (1)生態系を保全する区域の拡大と適正な管理
「より確実に生態系を保全するために自然公園区域や自然保護区、自然環境保全地域、その他の保護区の拡大を目指します。また、生態系を保全する区域について適正な管理を行うための仕組みを検討します。」
意見:様々な保護区の法制度を含むこれまでの管理の仕組みのレビューがあってはじめて、保護区の拡大へと繋がると考える。
提案:「より確実に生態系を保全するために、これまでの保護区の仕組みの検証を踏まえ、自然公園区域や自然保護区、自然環境保全地域、その他の保護区の拡大を目指します。また、生態系を保全する区域についてより適正な管理を行うための仕組みを検討します。」へと変更する。
原文箇所:p44〜45 第5章行動計画 (1) 生態系を保全する区域の拡大と適正な管理と(2)世界自然遺産への登録の推進
提案:仕組みや取組みのなかに「米軍との調整」を文言にいれ、位置づける。
理由:例えば、やんばるの森における保全区域の拡大と適正な管理は、米軍との調整なしには行えない。これは自然遺産登録においてもあてはまる。世界遺産登録に必要な、環境保全の担保措置は少なくとも「米軍との調整」なしにはできないと考える。
原文箇所:p46 (3)希少野生生物の保全
「天然記念物の最新の生息状況調査を行う。また、その結果をもとにした保護策を検討する」
提案:天然記念物の最新の棲息状況調査と、これまでの関係法令や条例(制度)の効果を検証し、その結果をもとにした保護策を検討する」という趣旨の文言にする。
理由:これまでの条例や仕組みのreview(検討)を行うことは不可欠であり、そのことを、文言でも示すべきであると考える。「最新の生息状況調査」という文言に、これまでの法、条例の仕組みの検証という意味も入っているという議論もあると思うが、仕組みの検証については明確に示されるべきだと考える。
原文箇所:p47 2 生物多様性を保全・維持し、再生する
「生物多様性を保全・維持し、再生するため、水質汚濁防止対策や海岸漂着ごみ対策による陸域・水辺環境の保全、関係者の連携による赤土等の流出防止への取り組み、及び開発事業における環境配慮等により、生物多様性の保全・維持、そして再生につなげます。また、産学官が連携し生物多様性の保全・維持・再生につながる技術開発等に取り組みます。」
提案1:この部分に、「数値目標を設定し」という趣旨の文言をいれる。
理由:数値目標の設定は重要であり、策定検討委員会でも議論されてきた。すべての項目において数値目標が設定できるわけではないが、取組みの基本方針として、その設定は大切であると考える。
提案2:関係部署においていろいろな保全の為の計画が、地域戦略と同時進行で作成され、地域戦略の中でも言及されている。この地域戦略が策定される時点で、そのような計画においての数値目標が設定されていれば、重要な或はシンボリックな項目の数値目標については、地域戦略の行動計画のなかでも示してはどうか。
原文箇所:p48
「・中城湾港は、”みなととまち”の形成を図るため、住民の散策・休息の場として、また海辺やマリーナ等の雰囲気を楽しめる場として緑地の整備を行なった」
意見:「行った」という過去形の文言は、行動計画の他の部分ではみられず、唐突に思える。
提案:「整備を行った緑地のモニタリングと管理を行う」あるいは「整備を行った緑地とその周りの環境における生物多様性のモニタリングと保全を行う」という趣旨の文言に変更する。
原文箇所:p51 (4) 環境影響評価制度の充実
「開発事業等による環境への影響を低減するため、沖縄の環境特性や社会状況の変化等を踏まえた上で、環境影響評価制度の見直しを検討します。」
意見:この文言では、具体的に現在のアセス制度では、どのような見直しが必要なのかが全くわからない。充実の方向性として、「情報公開」と「市民参画」ということへ言及してもらいたい。
原文箇所:p52 5自然環境の再生 「サンゴ礁の保全再生」 「干潟・湿地等水辺環境の再生」
意見:「保全再生」と「再生」という言葉が使用されており、違和感がある。もし同じ意味で使われているのなら、統一する必要があるし、異なる意味があり2つの表現が使われているならば、その違いを説明してもらいたい。
原文箇所:P54 (1)生物多様性を活用したバイオ産業の振興
「沖縄の生物資源を活用した技術の研究・開発を進め、バイオ産業の振興を図ります。また、産学官の共同で技術開発等を行い、県内企業等による研究・商品開発を促進します。」「ア 生物資源の産業への利用促進」
意見:生物資源の活用による産業の振興により、沖縄の「生物多様性」の保全、維持、再生にも繋がること、またその産業の振興が金銭的にも生物多様性の維持・保全の面においても、地域(県内企業と地域は必ずしも同じではない)に還元されることへの視点が欠けていると考える。
提案:「沖縄の生物資源を活用した技術の研究・開発を進め、バイオ産業の振興を図り、沖縄の生物多様性の保全や再生へと繋げます」「生物資源の産業への利用促進と利益の公正な配分」
原文箇所:p-55-7: 4 生物多様性に対する認識の向上と県民参加を促す
「生物多様性に対する認識の向上と県民参加を促すため、情報発信の拡大を図ります。また、環境教育等により様々な主体による活動の拡大や、生物多様性への理解の促進を図ります。さらに、これらの諸活動を知らせ、繋げ、育て、広げていく取り組みを促進します。」
意見と提案1:委員会でも議論されたとおり、ここは基本戦略を反映させる形で、「生物多様性に対する認識の向上」と「生物多様性保全に関する取組みに県民の参加を促す」に分ける。
意見と提案2:委員会でも議論された通り、沖縄の生物多様性の状況と、過去・現在における活用についての「調査」はまだまだであると考える。情報発信、認識の向上のために「調査を行う」とういう趣旨の文言をいれる。
原文箇所:p55 (1) 情報発信と拠点の強化
「地域環境センター等の既存施設を活用したセミナーを開催する等、生物多様性に関する情報発信や啓発活動を身近な拠点で実施することにより、県民等への情報発信の強化を図ります。」
意見と提案1: 下部の中項目ではアとイに別れているが、この文言からはイの「新たな機構の創設及びネットワーク化」については分からない。それが分かるような表現にするべきだと考える。
意見と提案2: 「地域環境センター等の既存施設を活用した」とあるが、既存の施設とは何か、例えば大学等の施設も想定しているのかが分かりにくい。ここでの「既存施設」のイメージがもう少し分かり易くなるような表現を使って欲しい。
意見と提案3:委員会では、中項目イの「新たな機構」にあたる「生物多様性プラザ/センター」について議論された。新たな機構についてもう少し具体的に記述するべきだと考える。また、新たな機構の役割は、県民理解の向上のための普及啓発だけでは不十分であり、生物多様性現状把握のための調査を手がける「情報収集」機能も必要である。収集情報に基づき、保護区拡大を図る科学的知を得て、現状を県民に伝えるなどの"核となる"事業を推進することを明確に記述して欲しい。さらには、アで述べられている「既存の施設」と「新たな機構」の関係を示すような文言が必要であると考えるが、その場合、圏域における施設との関係についても、示される文言が必要である。
意見と提案4:情報の発信を行うには、調査を通して情報を収集する能力を持つ人材と、その集めた情報をネットやその他の媒体を通して発信する能力を持つ人材が必要である。中項目ウとして、人材育成についても言及して欲しい。
原文箇所:p56 (2) 様々な主体による活動の拡大
「市町村や地域コミュニティ単位で行われている生物多様性の保全に関わる活動や、企業、生産者、団体等による生物多様性の保全の取組への支援、生物多様性に関する活動事例を広く公表することにより、様々な主体による活動の拡大を図ります。」
意見:様々な主体による活動の拡大は大切であるが、その活動における連携/調整は同様に大切であると考える。特に活動が行われることにより利益関係の問題が生じる場合は、特にその連携/調整は必用である。同時にそのようなコーディネーターの役割を行う人材の育成も大切だと考える。
提案:「活動の調整/提携」「活動の調整/提携」というような趣旨の文言をいれ、さらにはそのような人材な育成も行うことを示す文言をいれる。
その他:
1)p-58- 第2節 圏域別重点施策及び取組については、時間が足りなくてまだ見直せていません。
これからも意見/提案の提出が可能でしょうか?
2)委員会でも言及したが、庁内会議への知事公室・基地対策課の参加が必要である。
3)策定検討委員会のように、庁内会議を公開する形で行って欲しい。様々な利害関係や協力関係会が予想される庁内会議のプロセスや議論の内容が透明化することで、おきなわ戦略対しての市民・住民の関心も高まり、より室の高いものができると考える。
4)推進体制については内容が出来上がり次第、意見/提案を行う。
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
吉川秀樹
以下、「生物多様性おきなわ戦略(仮)」第4稿への意見と提案を述べます。なお私がこれまで、第1稿〜3.5稿について提出した意見の中で、その対応が「継続」となっているものについては基本的に省略しますが、これまでの意見がより具体的に反映されるであろうと考える箇所においては再度、意見/提案を述べています。
原文箇所:p22 (1)—2課題
「米軍基地の問題への対応」
意見:北部圏域の米軍基地/演習場の問題を考慮して、もう少し具体的な記述が必要だと考える。
提案:「米軍基地における環境問題へのJapan Environmental Governing Standards「日本環境管理基準」の実質的適用と米軍との協力体制 の欠如」とういう趣旨の文言を入れる。
原文箇所:p25 (2)-2課題
意見:中南部圏域の課題においても米軍基地問題についての言及が必要ではないか。
理由:中南部には返還予定の米軍基地があり、返還、跡地利用の際の汚染除去や自然環境回復や再生の課題がある。
提案:「返還予定の米軍基地の汚染除去や自然環境の回復や再生」という趣旨の文言を入れる。
原文箇所:p36 2 望ましい地域のイメージ (1)北部圏域
意見:海についての記述が少ない。サンゴ以外の海洋生物に対する言及が必要だと考える。ワークショップがやんばるの森で開かれ、その時の議論は、やんばるの森で開かれたこともあり森林関係に集中していたが、それが北部圏域の「望ましい地域のイメージ」の記述に反映しているのではないか。
提案1: 「ジュゴンやウミガメのような貴重種の保全が行われている」という趣旨の文言をいれる。
理由:生物多様性国家戦略においても「豊かな生命を育む沿岸域は、多様で豊富な魚介類を持続的に供給するとともに、北の海ではアザラシが、南の海ではジュゴンが泳ぐ姿が見られるなど、人間と自然の共生のもとに健全な生態系を保っている」とあり、現在日本において、唯一ジュゴンが棲息し、その保護の活動が行われてきた北部圏域の「望ましい地域のイメージ」でも、言及されるべきだと考える。
提2:「海や川の保全が、エコツアーリズムと連携して行われている」という趣旨の文言をいれる。
理由:実際の海や川の保全の取組みが、エコツーリズムと連携して行われ始めており、それは大切であると考える。
原文箇所: p41 2短期目標(2022年(10年)
「生物多様性を保全・再生し、生物多様性の恵みを継続的に享受する」
意見: これは生物多様性地域戦略の全体的な目標と殆ど同じであり、短期目標としては分かりにくい。
提案:「生物多様性を保全・再生し、生物多様性の恵みを継続的に享受する制度基盤を確立する。」という趣旨の文言にする。
原文箇所:p42 3 社会経済的仕組みの考慮
「生物多様性を保全することが経済的な負担となるのではなく、保全することが付加価値となって経済的に有利となる仕組みを検討する。」
提案:「保全(活動)を新たなる公共の事業の仕組みに位置づけることを検討する」といった趣旨の文言を加えてはどうか。
理由:保全により付加価値を生み出すことは時間がかかる場合が多い。むしろ保全(活動)自体を、縮小されていく公共工事に変わる公共事業としての経済活動とすることがまず必要だと考える。
原文箇所:p43 第5節 基本戦略
提案: 6として「上記の基本戦略を進めるための財源の確保と適切な運用を図る」という趣旨の文言を加える。
理由:地域戦略において、財源へ確保と運用についての言及は不可欠だと考える。
原文箇所:p44 (1)生態系を保全する区域の拡大と適正な管理
「より確実に生態系を保全するために自然公園区域や自然保護区、自然環境保全地域、その他の保護区の拡大を目指します。また、生態系を保全する区域について適正な管理を行うための仕組みを検討します。」
意見:様々な保護区の法制度を含むこれまでの管理の仕組みのレビューがあってはじめて、保護区の拡大へと繋がると考える。
提案:「より確実に生態系を保全するために、これまでの保護区の仕組みの検証を踏まえ、自然公園区域や自然保護区、自然環境保全地域、その他の保護区の拡大を目指します。また、生態系を保全する区域についてより適正な管理を行うための仕組みを検討します。」へと変更する。
原文箇所:p44〜45 第5章行動計画 (1) 生態系を保全する区域の拡大と適正な管理と(2)世界自然遺産への登録の推進
提案:仕組みや取組みのなかに「米軍との調整」を文言にいれ、位置づける。
理由:例えば、やんばるの森における保全区域の拡大と適正な管理は、米軍との調整なしには行えない。これは自然遺産登録においてもあてはまる。世界遺産登録に必要な、環境保全の担保措置は少なくとも「米軍との調整」なしにはできないと考える。
原文箇所:p46 (3)希少野生生物の保全
「天然記念物の最新の生息状況調査を行う。また、その結果をもとにした保護策を検討する」
提案:天然記念物の最新の棲息状況調査と、これまでの関係法令や条例(制度)の効果を検証し、その結果をもとにした保護策を検討する」という趣旨の文言にする。
理由:これまでの条例や仕組みのreview(検討)を行うことは不可欠であり、そのことを、文言でも示すべきであると考える。「最新の生息状況調査」という文言に、これまでの法、条例の仕組みの検証という意味も入っているという議論もあると思うが、仕組みの検証については明確に示されるべきだと考える。
原文箇所:p47 2 生物多様性を保全・維持し、再生する
「生物多様性を保全・維持し、再生するため、水質汚濁防止対策や海岸漂着ごみ対策による陸域・水辺環境の保全、関係者の連携による赤土等の流出防止への取り組み、及び開発事業における環境配慮等により、生物多様性の保全・維持、そして再生につなげます。また、産学官が連携し生物多様性の保全・維持・再生につながる技術開発等に取り組みます。」
提案1:この部分に、「数値目標を設定し」という趣旨の文言をいれる。
理由:数値目標の設定は重要であり、策定検討委員会でも議論されてきた。すべての項目において数値目標が設定できるわけではないが、取組みの基本方針として、その設定は大切であると考える。
提案2:関係部署においていろいろな保全の為の計画が、地域戦略と同時進行で作成され、地域戦略の中でも言及されている。この地域戦略が策定される時点で、そのような計画においての数値目標が設定されていれば、重要な或はシンボリックな項目の数値目標については、地域戦略の行動計画のなかでも示してはどうか。
原文箇所:p48
「・中城湾港は、”みなととまち”の形成を図るため、住民の散策・休息の場として、また海辺やマリーナ等の雰囲気を楽しめる場として緑地の整備を行なった」
意見:「行った」という過去形の文言は、行動計画の他の部分ではみられず、唐突に思える。
提案:「整備を行った緑地のモニタリングと管理を行う」あるいは「整備を行った緑地とその周りの環境における生物多様性のモニタリングと保全を行う」という趣旨の文言に変更する。
原文箇所:p51 (4) 環境影響評価制度の充実
「開発事業等による環境への影響を低減するため、沖縄の環境特性や社会状況の変化等を踏まえた上で、環境影響評価制度の見直しを検討します。」
意見:この文言では、具体的に現在のアセス制度では、どのような見直しが必要なのかが全くわからない。充実の方向性として、「情報公開」と「市民参画」ということへ言及してもらいたい。
原文箇所:p52 5自然環境の再生 「サンゴ礁の保全再生」 「干潟・湿地等水辺環境の再生」
意見:「保全再生」と「再生」という言葉が使用されており、違和感がある。もし同じ意味で使われているのなら、統一する必要があるし、異なる意味があり2つの表現が使われているならば、その違いを説明してもらいたい。
原文箇所:P54 (1)生物多様性を活用したバイオ産業の振興
「沖縄の生物資源を活用した技術の研究・開発を進め、バイオ産業の振興を図ります。また、産学官の共同で技術開発等を行い、県内企業等による研究・商品開発を促進します。」「ア 生物資源の産業への利用促進」
意見:生物資源の活用による産業の振興により、沖縄の「生物多様性」の保全、維持、再生にも繋がること、またその産業の振興が金銭的にも生物多様性の維持・保全の面においても、地域(県内企業と地域は必ずしも同じではない)に還元されることへの視点が欠けていると考える。
提案:「沖縄の生物資源を活用した技術の研究・開発を進め、バイオ産業の振興を図り、沖縄の生物多様性の保全や再生へと繋げます」「生物資源の産業への利用促進と利益の公正な配分」
原文箇所:p-55-7: 4 生物多様性に対する認識の向上と県民参加を促す
「生物多様性に対する認識の向上と県民参加を促すため、情報発信の拡大を図ります。また、環境教育等により様々な主体による活動の拡大や、生物多様性への理解の促進を図ります。さらに、これらの諸活動を知らせ、繋げ、育て、広げていく取り組みを促進します。」
意見と提案1:委員会でも議論されたとおり、ここは基本戦略を反映させる形で、「生物多様性に対する認識の向上」と「生物多様性保全に関する取組みに県民の参加を促す」に分ける。
意見と提案2:委員会でも議論された通り、沖縄の生物多様性の状況と、過去・現在における活用についての「調査」はまだまだであると考える。情報発信、認識の向上のために「調査を行う」とういう趣旨の文言をいれる。
原文箇所:p55 (1) 情報発信と拠点の強化
「地域環境センター等の既存施設を活用したセミナーを開催する等、生物多様性に関する情報発信や啓発活動を身近な拠点で実施することにより、県民等への情報発信の強化を図ります。」
意見と提案1: 下部の中項目ではアとイに別れているが、この文言からはイの「新たな機構の創設及びネットワーク化」については分からない。それが分かるような表現にするべきだと考える。
意見と提案2: 「地域環境センター等の既存施設を活用した」とあるが、既存の施設とは何か、例えば大学等の施設も想定しているのかが分かりにくい。ここでの「既存施設」のイメージがもう少し分かり易くなるような表現を使って欲しい。
意見と提案3:委員会では、中項目イの「新たな機構」にあたる「生物多様性プラザ/センター」について議論された。新たな機構についてもう少し具体的に記述するべきだと考える。また、新たな機構の役割は、県民理解の向上のための普及啓発だけでは不十分であり、生物多様性現状把握のための調査を手がける「情報収集」機能も必要である。収集情報に基づき、保護区拡大を図る科学的知を得て、現状を県民に伝えるなどの"核となる"事業を推進することを明確に記述して欲しい。さらには、アで述べられている「既存の施設」と「新たな機構」の関係を示すような文言が必要であると考えるが、その場合、圏域における施設との関係についても、示される文言が必要である。
意見と提案4:情報の発信を行うには、調査を通して情報を収集する能力を持つ人材と、その集めた情報をネットやその他の媒体を通して発信する能力を持つ人材が必要である。中項目ウとして、人材育成についても言及して欲しい。
原文箇所:p56 (2) 様々な主体による活動の拡大
「市町村や地域コミュニティ単位で行われている生物多様性の保全に関わる活動や、企業、生産者、団体等による生物多様性の保全の取組への支援、生物多様性に関する活動事例を広く公表することにより、様々な主体による活動の拡大を図ります。」
意見:様々な主体による活動の拡大は大切であるが、その活動における連携/調整は同様に大切であると考える。特に活動が行われることにより利益関係の問題が生じる場合は、特にその連携/調整は必用である。同時にそのようなコーディネーターの役割を行う人材の育成も大切だと考える。
提案:「活動の調整/提携」「活動の調整/提携」というような趣旨の文言をいれ、さらにはそのような人材な育成も行うことを示す文言をいれる。
その他:
1)p-58- 第2節 圏域別重点施策及び取組については、時間が足りなくてまだ見直せていません。
これからも意見/提案の提出が可能でしょうか?
2)委員会でも言及したが、庁内会議への知事公室・基地対策課の参加が必要である。
3)策定検討委員会のように、庁内会議を公開する形で行って欲しい。様々な利害関係や協力関係会が予想される庁内会議のプロセスや議論の内容が透明化することで、おきなわ戦略対しての市民・住民の関心も高まり、より室の高いものができると考える。
4)推進体制については内容が出来上がり次第、意見/提案を行う。
Posted by 沖縄BD at 05:34│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。